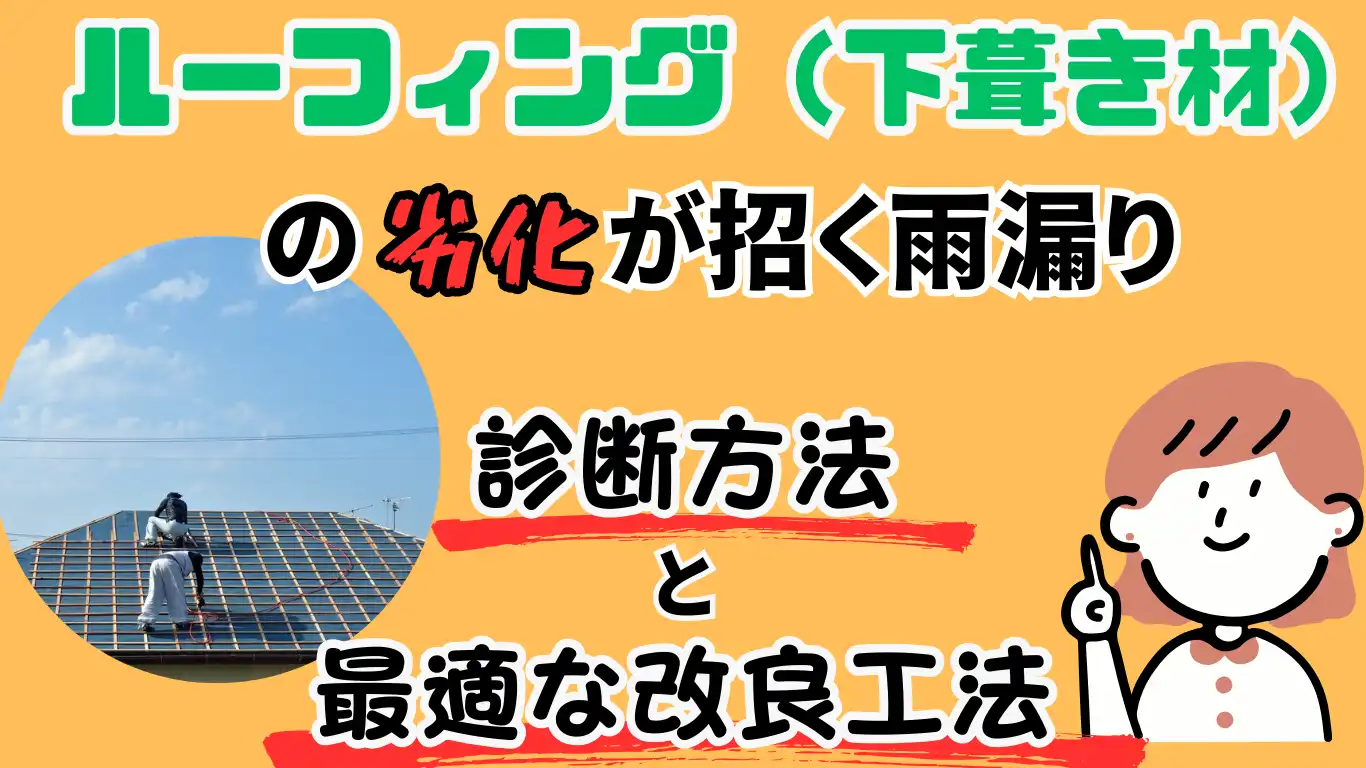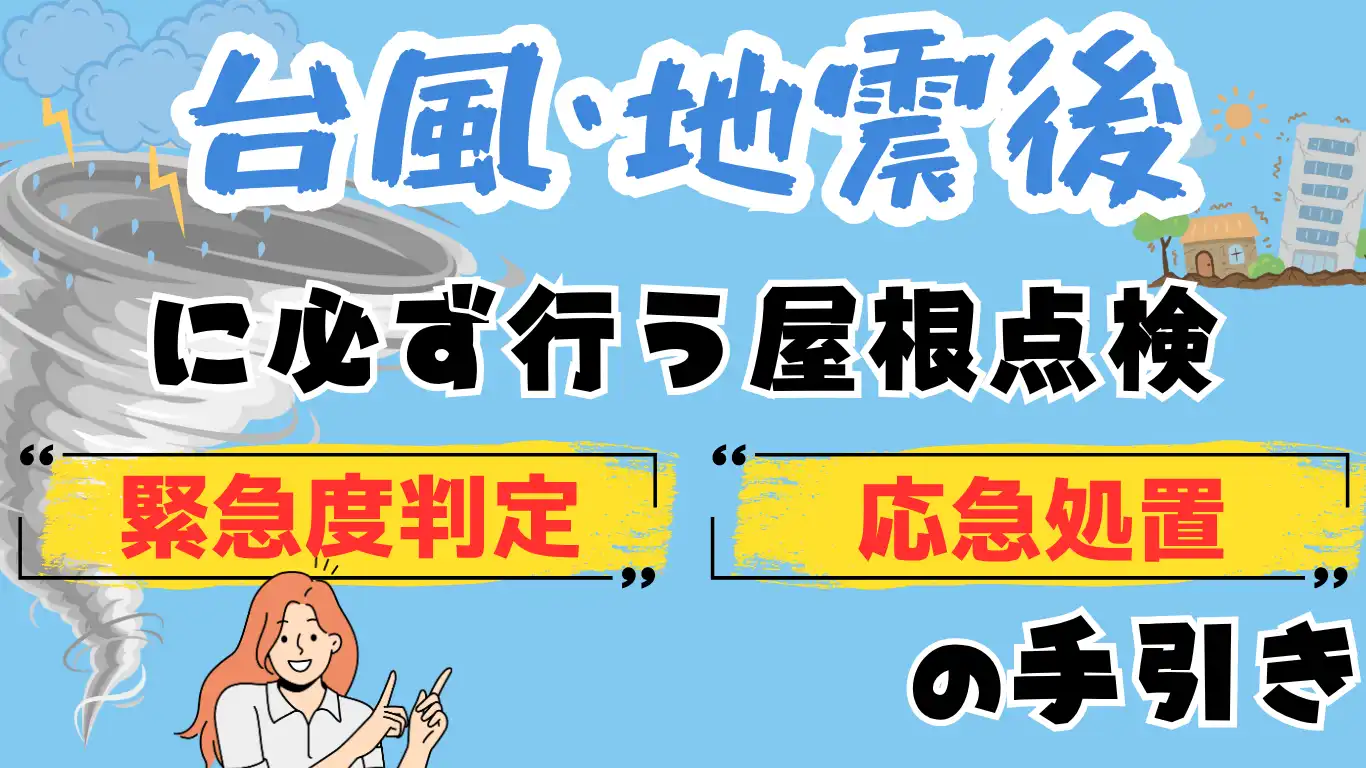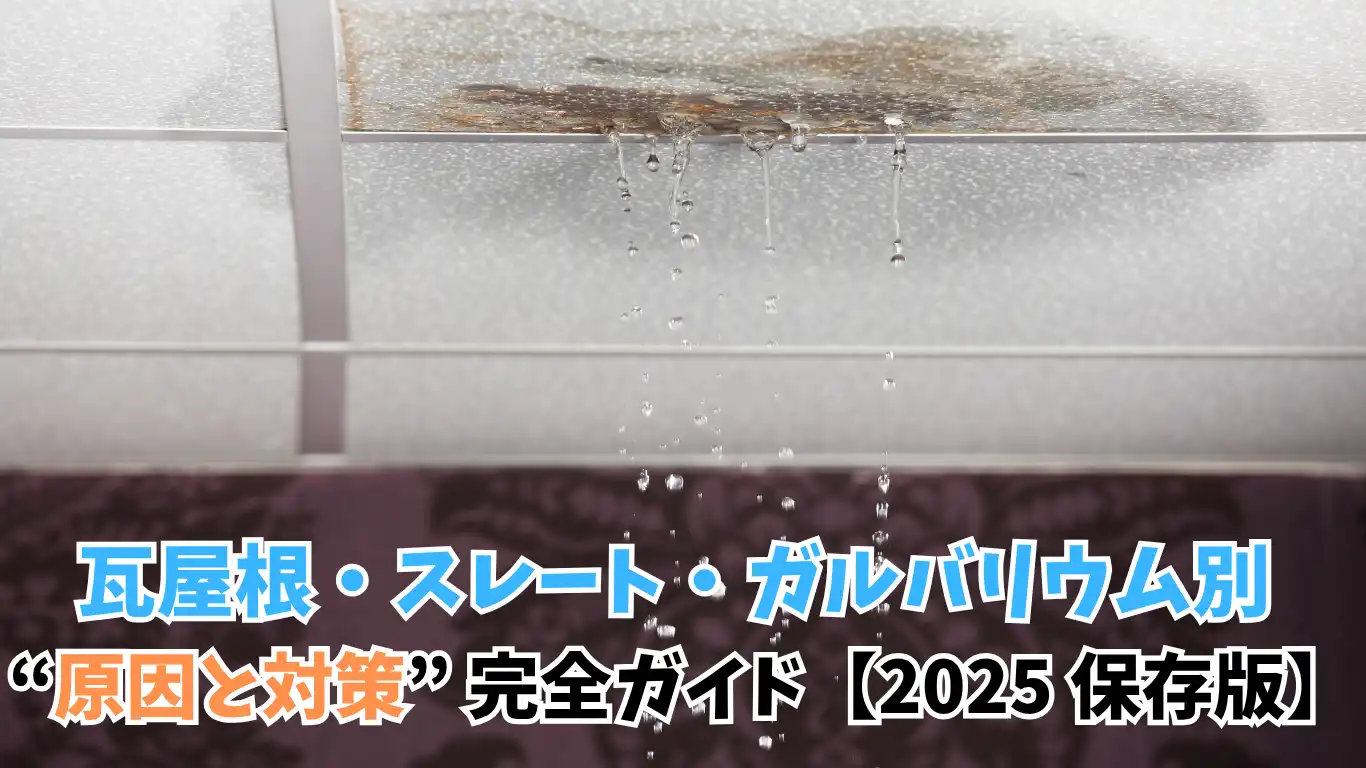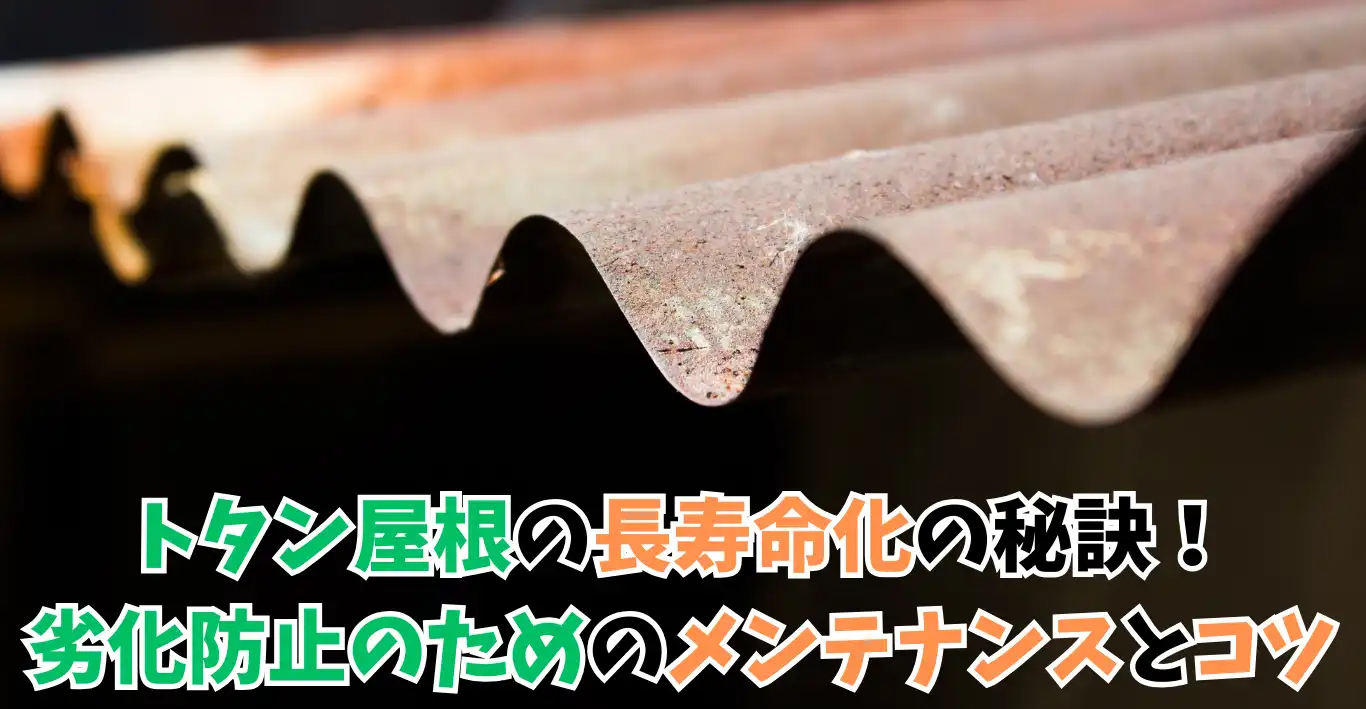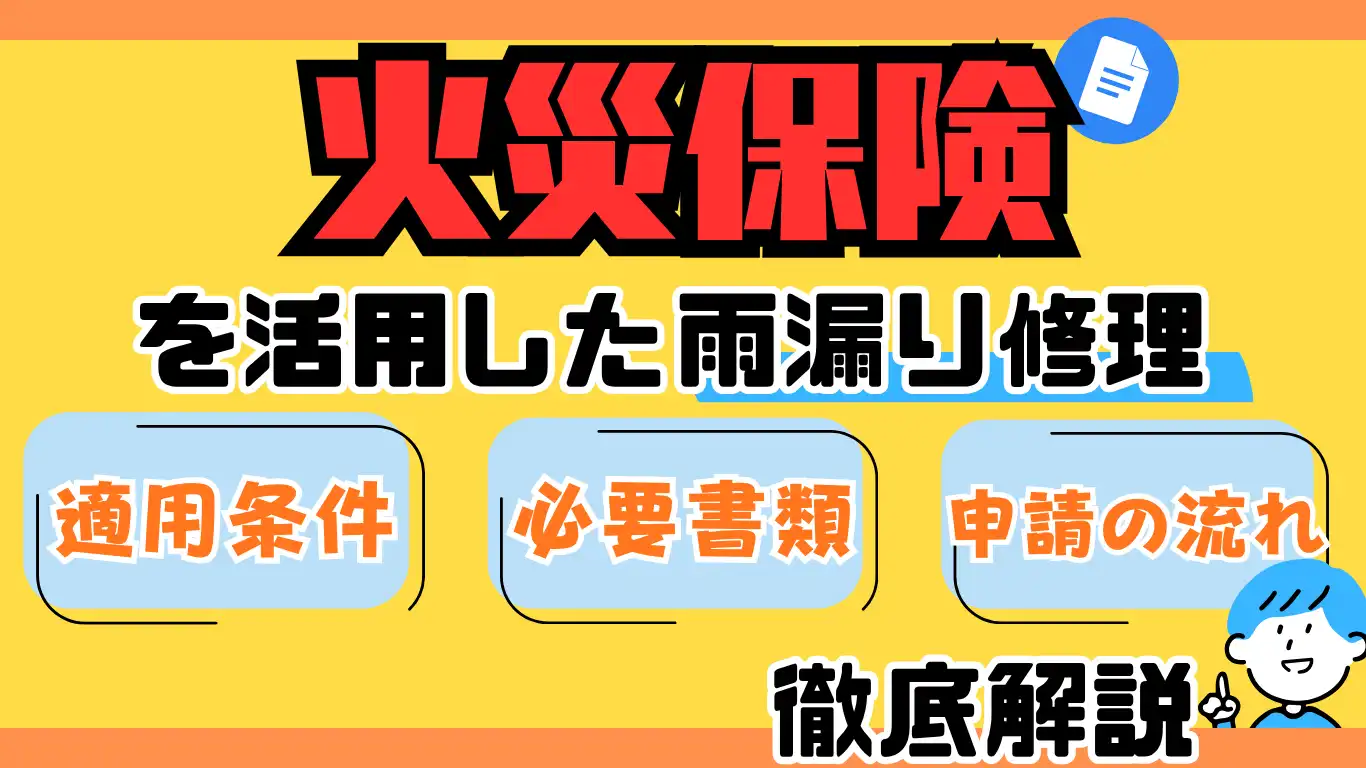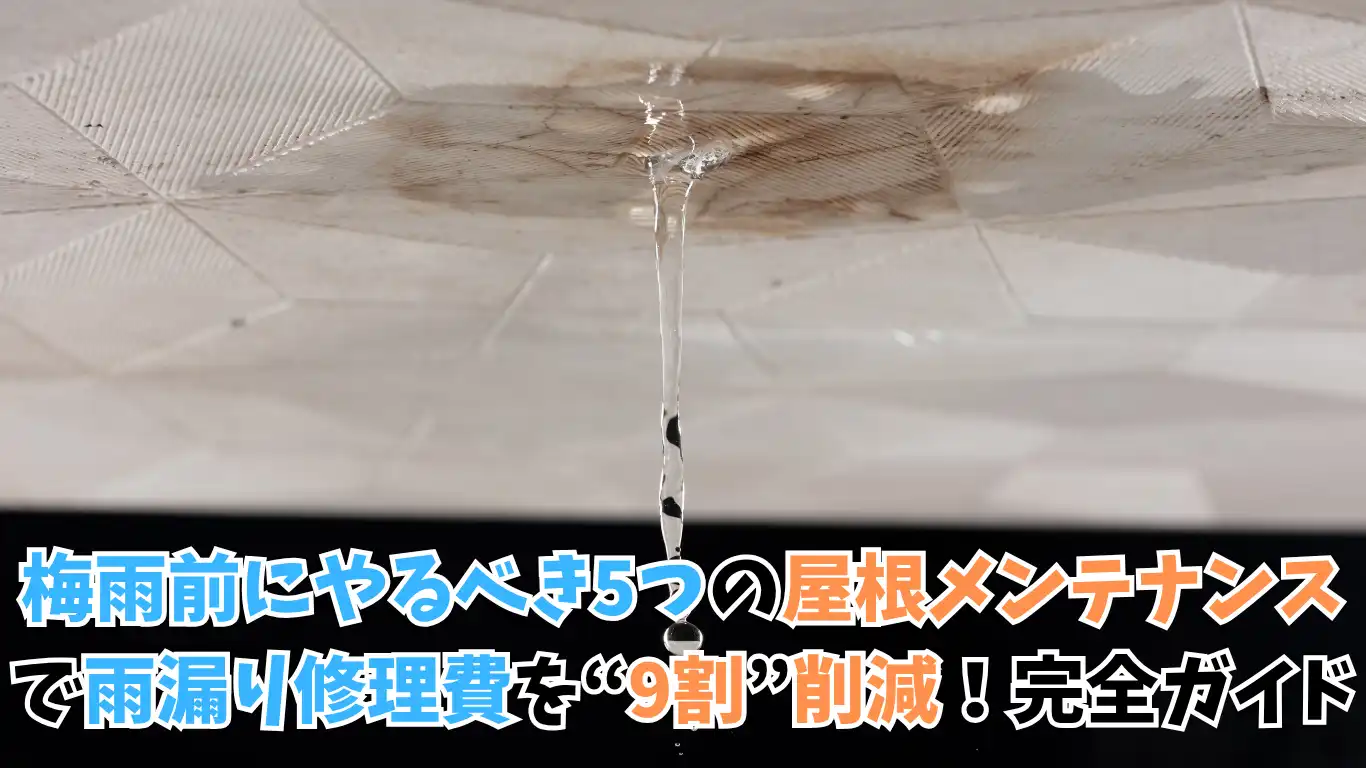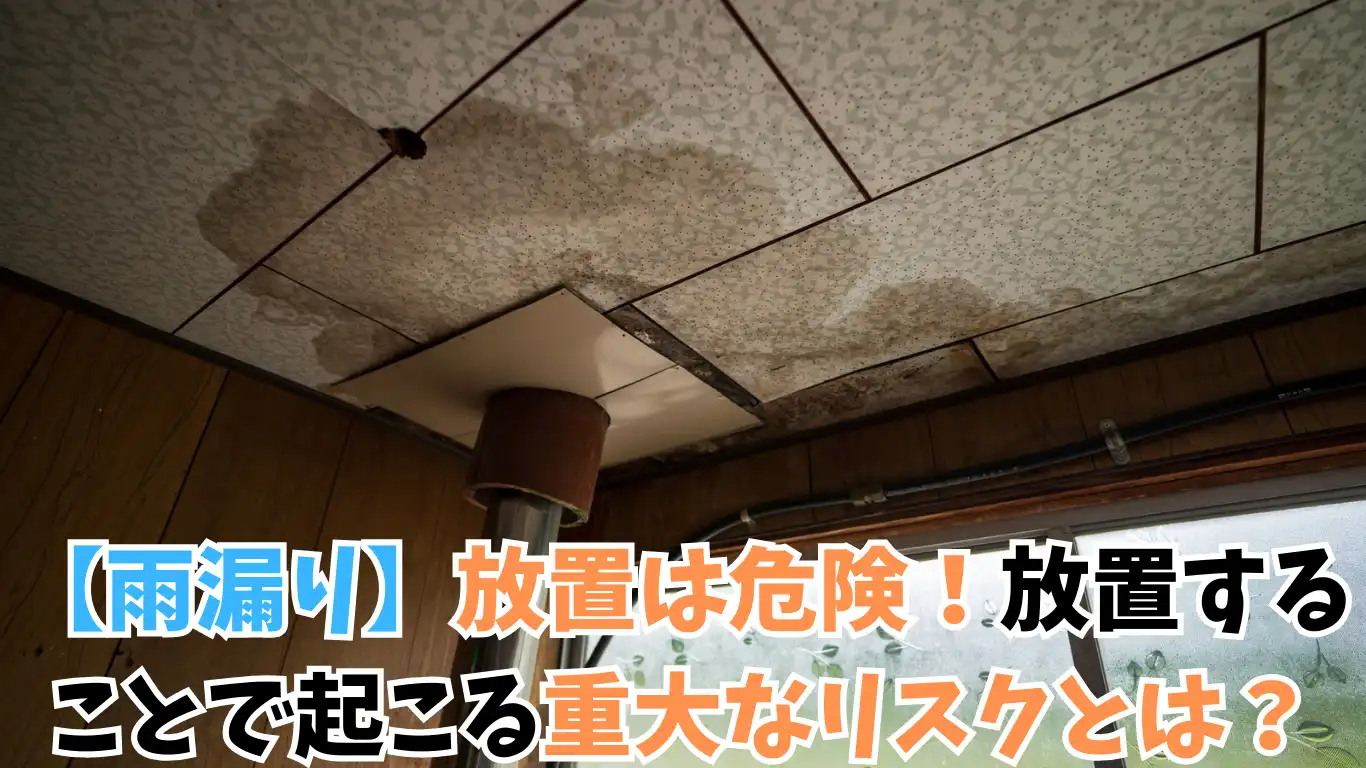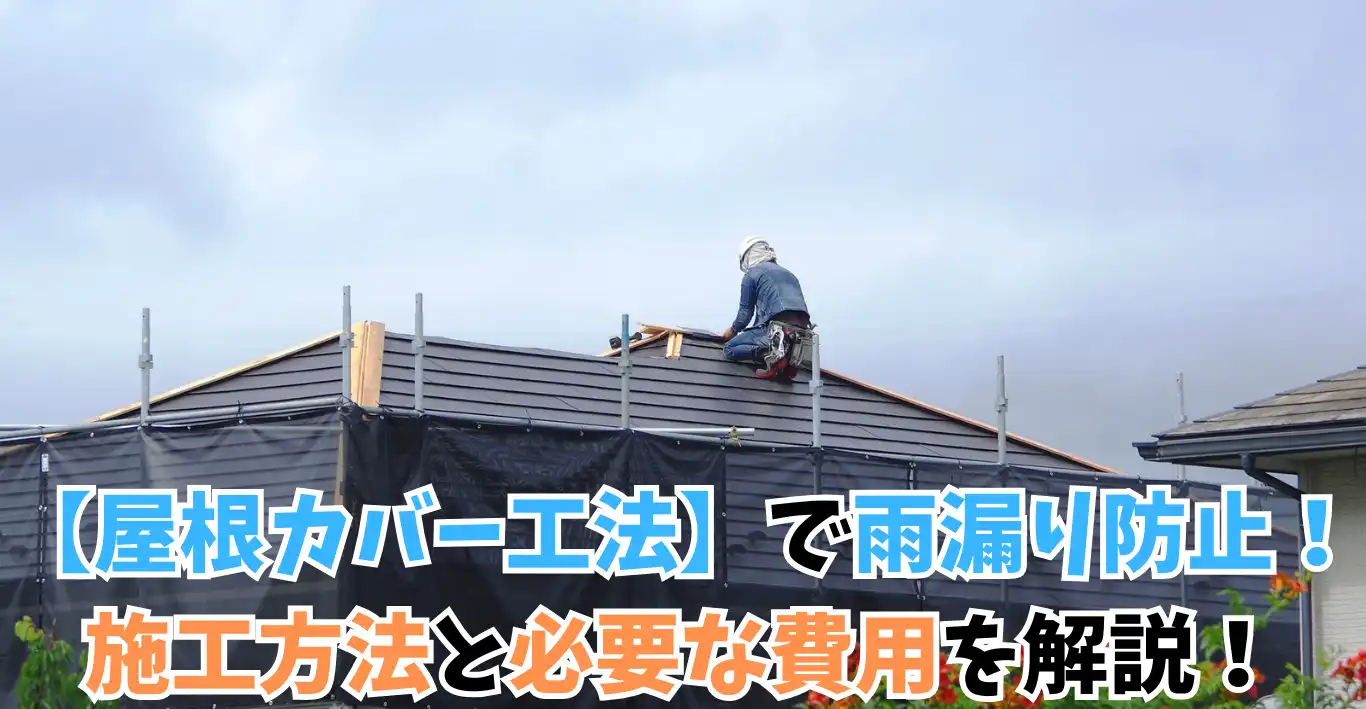まずやるべきこと/NG行為

まずやるべきこと
- 1. 安全確保と証拠保全:強風・降雨時に屋根へ上らない。室内のシミ位置・発生日時・雨量/風向を写真付きで記録(浸入箇所は真上とは限らない)。
- 2. 水の迂回:室内はバケツ・シートで被害拡大を抑制。
- 3. 専門家へ相談:原因特定は難易度が高い。散水試験を実施できる実務経験者に依頼。
絶対NG
- ・原因不明のまま穴開け/コーキング(水の出口を塞ぎ内部滞水→腐朽/シロアリ加速)。
- ・無装備の高所作業(滑落リスク)。フルハーネス等の安全対策なしで登らない。
ルーフィングの役割:一次防水との違い・雨水の流路と弱点

| 役割 | 部位 | 機能 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 一次防水 | 瓦・スレート・板金など屋根材 | 雨水を直接受け流し屋外へ排出 | 経年/風災で破損しやすい |
| 二次防水 | ルーフィング(下葺き材) | すり抜けた水を下地へ到達させず軒先へ排出 | 建物耐久の“最後の砦” |
弱点の要点
- ・水集中部(谷・壁際・天窓まわり等)は事故多発。
- ・立上げ不足は回り込みの主因。外壁透湿防水シートと連続させる。
- ・貫通部(釘・金物)は止水処理が甘いと浸入口に。
劣化サイン診断
室内兆候
- ・シミ位置は原因の真上と限らない(構造体・通気層を伝って移動)。
- ・腐朽臭/カビは長期湿潤のサイン。
- ・長雨後や強風時のみ出る:重ね不足・貫通部不具合の疑い。
専門診断の主手法
| 診断方法 | 目的 | 備考 |
|---|---|---|
| 散水試験 | 浸入経路の特定 | 恒久修理前に実施が基本 |
| サーモグラフィ | 温度差で濡れを可視化 | 散水と併用で有効 |
| 小屋裏点検/内視鏡 | 野地板や構造材の濡れ・腐朽・白蟻 | 損傷範囲の把握 |
| 含水率測定 | 濡れの定量化 | 強度低下の判断根拠 |
表①:症状⇔原因⇔診断方法マップ
| 症状(室内) | ルーフィング関連の原因 | 主な診断 |
|---|---|---|
| 天井の局所シミ | 谷・棟の破れ/重ね不足 | 散水試験、小屋裏点検 |
| 壁のシミ/クロス剥がれ | 壁際立上げ不足 | 散水試験、内視鏡 |
| 濡れ+腐朽臭/カビ | 経年劣化・結露滞留 | 含水率、サーモ |
| 強風/大雨時のみ大量浸水 | 釘穴シール不良、固定不良 | 散水試験、屋根上点検 |
劣化原因Top5

- 1. 経年硬化・熱伸縮:アスファルト系は硬化→微小破断。
- 2. 重ね代不足/流れ方向誤り:推奨100–200mm確保。下→上へ重ねる。
- 3. 留め付けピッチ/位置不良:指定場所以外の貫通やピッチ過大は浸水要因。目安100–150mm。
- 4. 谷・棟・開口部の処理不良:谷芯越え250mm以上の折返し、幅500–1000mmの増し張りが基本。開口/壁際は立上げ150mm以上。
- 5. 結露・湿気滞留:通気不足で野地腐朽。金属屋根は特に要配慮。
DIY可否マトリクス(安全判定)
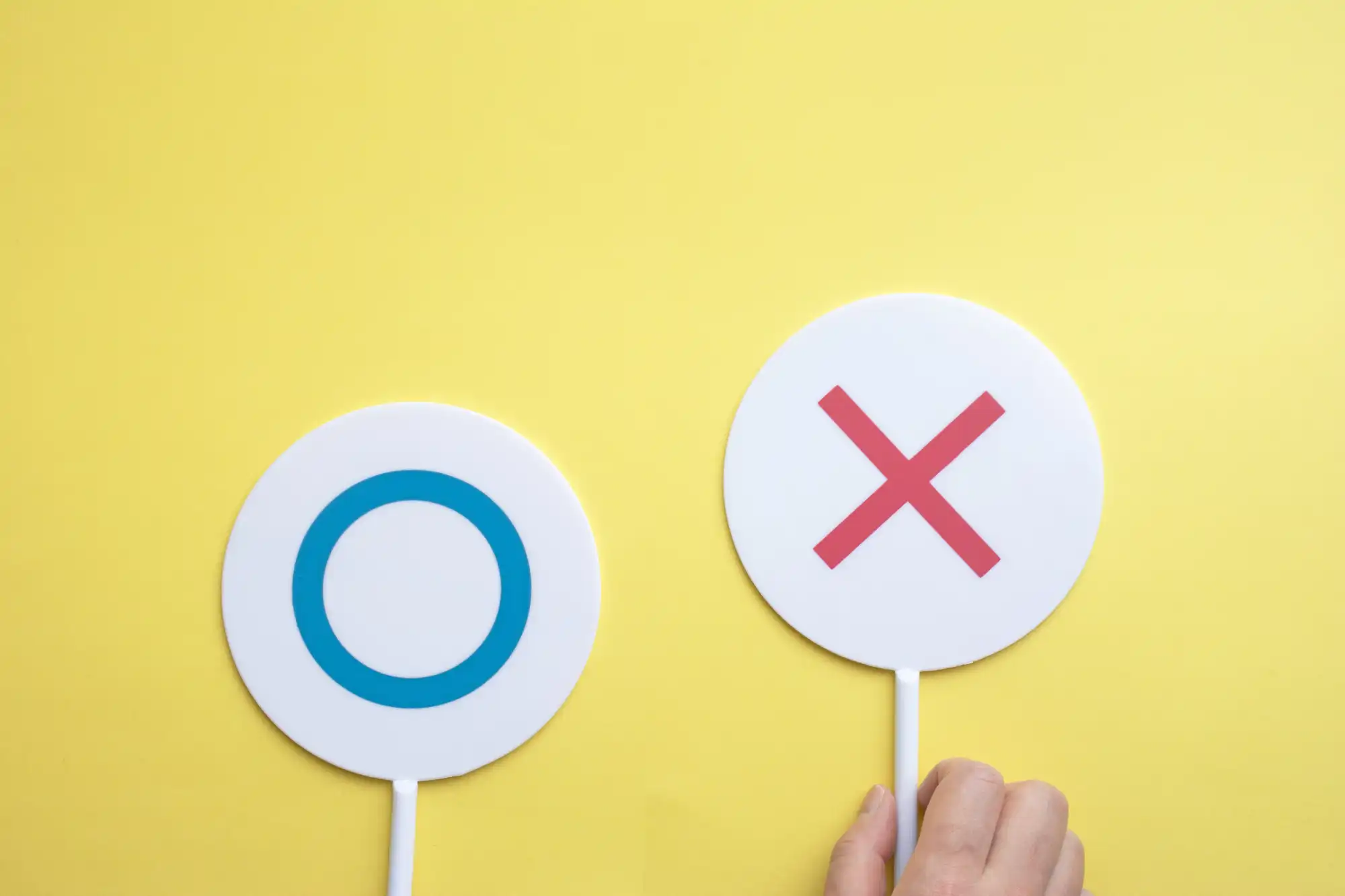
| 要因 | 屋根勾配 | 階数 | 損傷/気象 | 推奨 |
|---|---|---|---|---|
| 低リスク | 3寸未満 | 平屋 | 雨後の地上目視 | DIY応急(安全最優先) |
| 中リスク | 3–6寸 | 2階 | 釘浮き程度/目視困難 | 専門調査 |
| 高リスク | 6寸以上/短勾配 | 3階以上 | 広範囲破損/荒天時 | 業者専任(足場必須) |
応急30分

応急キット
- ・ブチル系両面粘着防水テープ(幅75mm以上)/ヘラ・ローラー
- ・ブルーシート#3000、ロープ、土のう
- ・(専門者向け)フルハーネス
手順
- 1. 安全確保(荒天・無装備で登らない)。
- 2. 疑い部位の目視(谷・棟・壁際・破損)。
- 3. ブチルで仮止水(しっかり圧着、シワ/浮き厳禁)。
- 4. シート養生(水の流れを阻害せず軒先へ誘導、風対策固定)。
恒久改修の正解
改修フロー
- 1. 既存屋根材撤去・下地点検
- 2. 野地板/構造材の腐朽補修・乾燥
- 3. 高耐久ルーフィング施工(改質アスファルト等)
- 4. 重ね代100–200mm/立上げ150mm以上/谷芯越え250mm以上を順守
- 5. 屋根材復旧(役物・取り合いの止水)
- 6. 通水試験10–20分で完了確認
施工要点
- 軒先→棟へ、下から上に重ねる。
- 留め付けは指定ピッチ100–150mm、水線内の貫通禁止。
- 壁側透湿防水シートと防水ラインを連続。
屋根材別の最適納まり

屋根材別最低勾配(目安)と留意点
| 屋根材 | 最低勾配(目安) | 納まりの要点 |
|---|---|---|
| 瓦(和/洋) | 3–4寸 | 瓦下へ回り込みやすい→釘穴シール性重視 |
| 化粧スレート | 3寸 | 釘穴・板間吹込み対策が要点 |
| 金属(横葺き) | 2–3寸 | 谷・棟の立上げと連続止水 |
| 金属(立平) | 0.5寸~ | ルーフィング上滞留/結露に注意、通気層+透湿材も選択肢 |
価格帯と見積内訳

表②:主要ルーフィング材の比較
| 材料名 | 通称 | 耐久 | 耐熱 | 初期コスト | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 改質アスファルト | ゴムアス | 高(20年以上) | 高 | 中~高 | 防水・伸縮・釘穴シールに優れる |
| アスファルトフェルト | 従来品 | 低~中(~10年) | 低 | 低 | 硬化しやすい |
| 透湿防水シート | 透湿ルーフィング | 中 | 中 | 中 | 湿気排出、通気設計と併用で効果 |
概算費用(目安)
- ・ルーフィング交換:3,000–6,000円/m²(撤去・復旧・下地補修で変動)
- ・足場:800–1,500円/m²(外周面積換算)
- ・散水試験:20,000–60,000円/回
見積“赤ペン”チェック
| 項目 | チェックポイント | 備考 |
|---|---|---|
| 材料仕様 | 製品名/等級(改質アス/JIS適合)の明記 | 性能差が大 |
| 施工範囲/数量 | 面積(m²)・役物長さ(m)の明記 | 一式回避 |
| 寸法仕様 | 重ね100–200mm/立上げ150mm以上の記載 | 納まり図を要求 |
| 下地補修 | 野地・構造補修の単価と条件 | 追加費の基準化 |
| 通水試験 | 10–20分の試験手順/費用を記載 | 成功確認の証拠 |
| 足場/産廃 | 設置・解体、処分費を分離計上 | 安全・法令対応 |
| 保証 | 年数と対象(雨漏り/材料) | 構造・雨水は10年目安 |
| 固定具/貫通対策 | SUS等材質、ブチル系テープ併用の有無 | 釘穴対策の明文化 |
| 換気/通気 | 通気層・換気棟提案の有無 | 結露対策が再発防止鍵 |
再発防止
- ・換気計画:透湿材+通気層(軒天換気・胴縁・換気棟)で湿気排出。外壁通気は隙間30mm以上が目安。
- ・落葉/積雪:谷/樋の堆積でオーバーフロー→定期清掃。積雪地は改質アス推奨。
- ・点検/保証:引渡し後10年の瑕疵担保範囲(構造・雨水)。高耐久材に合わせ定期点検+有償メンテで寿命延伸。
- ・保険:台風・積雪等の風災は対象になり得るが、経年劣化は対象外。時期特定・写真・業者報告書を整える。重大欠陥は不法行為20年の射程となるケースも。
チェックリスト
現地調査(点検)必須カットリスト
- 1. 重ね寸法(100–200mm)計測写真
- 2. 立上げ(150mm以上)の全景・近景
- 3. 端部/サッシフィンへのテープ密着で防水ライン連続
- 4. 貫通部の伸縮テープ等での止水状態
- 5. ルーフィング撤去時の野地/たるき腐朽確認
- 6. 谷部:谷芯越え250mm以上折返し・二重張りの証跡
- 7. 通水試験10–20分:散水状況+室内側の漏水無
応急キット
- ブルーシート(#3000)
- ブチル両面防水テープ(幅75mm以上)
- ロープ・土のう・養生テープ
- ヘラ/ローラー(圧着用)
表③:屋根材別の最低勾配基準と改修工法
| 屋根材 | 最低勾配(目安) | 低勾配のリスク | 推奨ルーフィング |
|---|---|---|---|
| 瓦(粘土瓦) | 3–4寸 | 瓦下への回り込み | 改質アス(釘穴シール性) |
| 化粧スレート | 3寸 | 釘穴/板間浸水 | 改質アス |
| 金属(立平) | 0.5–1寸 | ルーフィング上滞留/結露 | 改質アス or 透湿+通気層 |
| 金属(横葺き) | 2–3寸 | 継手吹き込み | 改質アス |
FAQ(よくある質問 10選)

Q1. 劣化したら必ず雨漏り?
A. 一次防水が健全なら表面化しにくいが、二次防水が劣化していると侵入時に即漏水・下地腐朽につながる。
Q2. 耐用年数は?
A. 従来フェルトは約10年、改質アスは20年以上が目安。
Q3. 屋根を剥がさず重ねられる?
A. カバー工法は可能だが、下地健全が前提。腐朽大なら撤去補修が必須。
Q4. 釘穴からの浸水対策は?
A. 改質アス採用+ブチル両面テープ先張りで下地と密着、止水性を高める。
Q5. シミの真上が原因?
A. 限らない。水は移動するため、散水試験などで実証が必要。
Q6. 「ルーフィング交換一式」見積は?
A. 不可。材料名・面積・立上げ/重ね寸法・下地補修・試験・保証の内訳提示を要求。
Q7. なぜ結露が原因に?
A. 湿潤継続で腐朽→保持力低下→白蟻の連鎖。通気計画が再発防止の鍵。
Q8. 壁際の最重要ポイントは?
A. 立上げ150mm以上+外壁透湿防水シートと連続させること。
Q9. 改修後の通水試験は必要?
A. 必須。隠れてしまう層の確実性を10–20分の試験で確認。
Q10. 改質アス vs 透湿、どちら?
A. 一般傾斜は改質アス。金属屋根などは透湿+通気層の併用も有効。