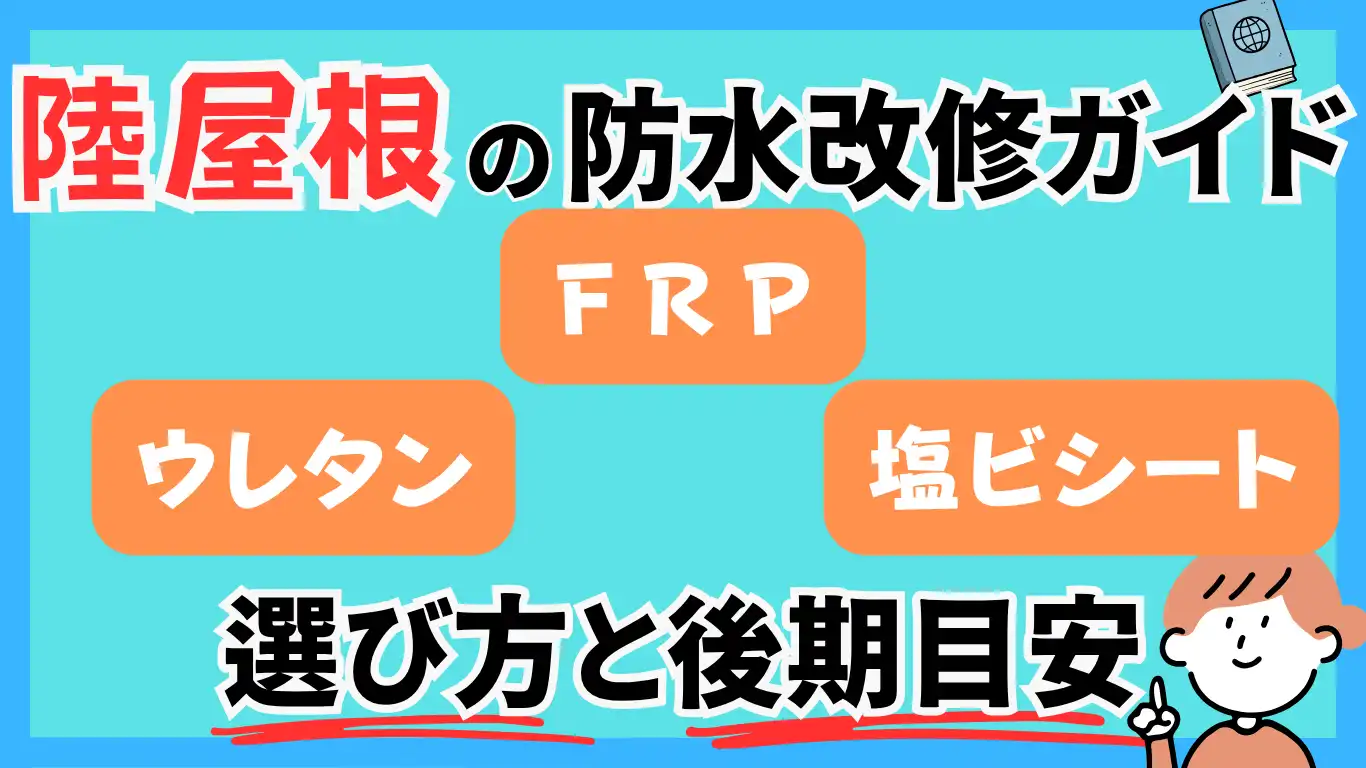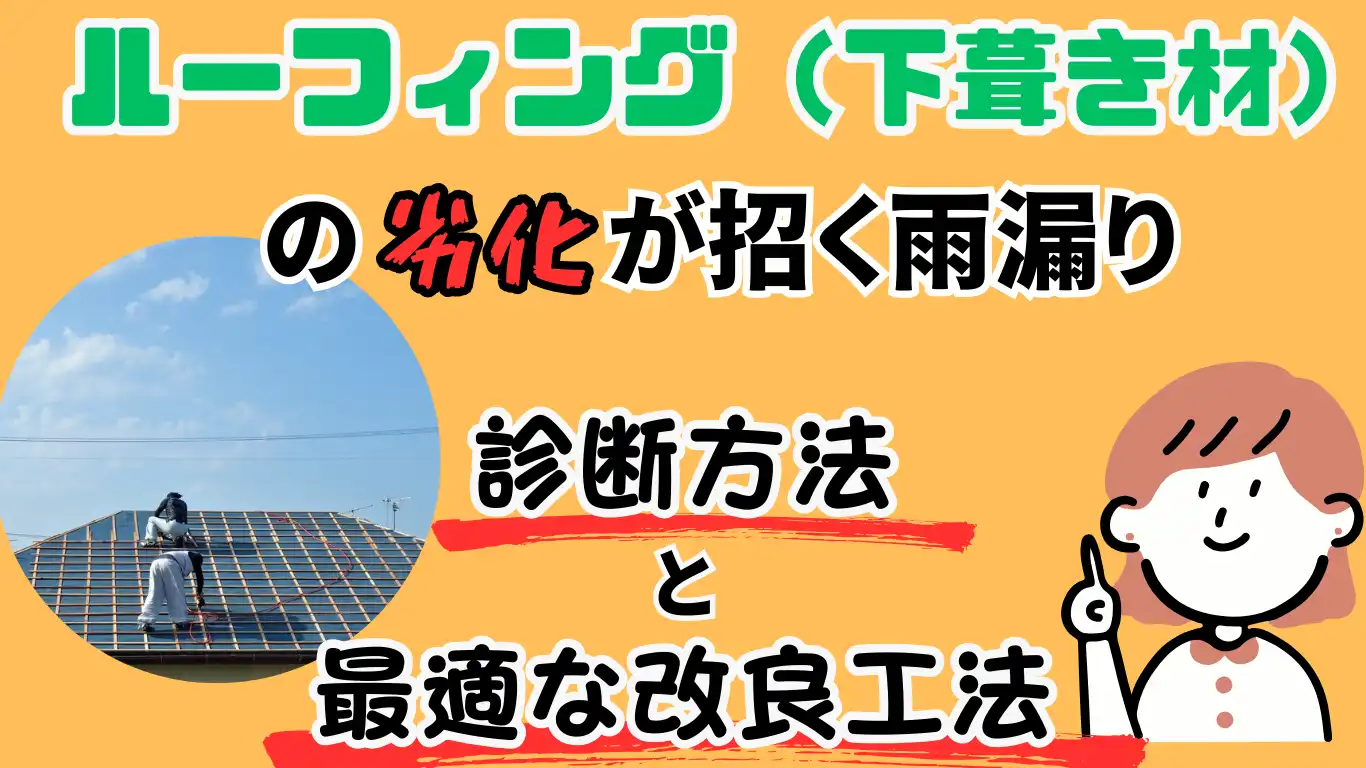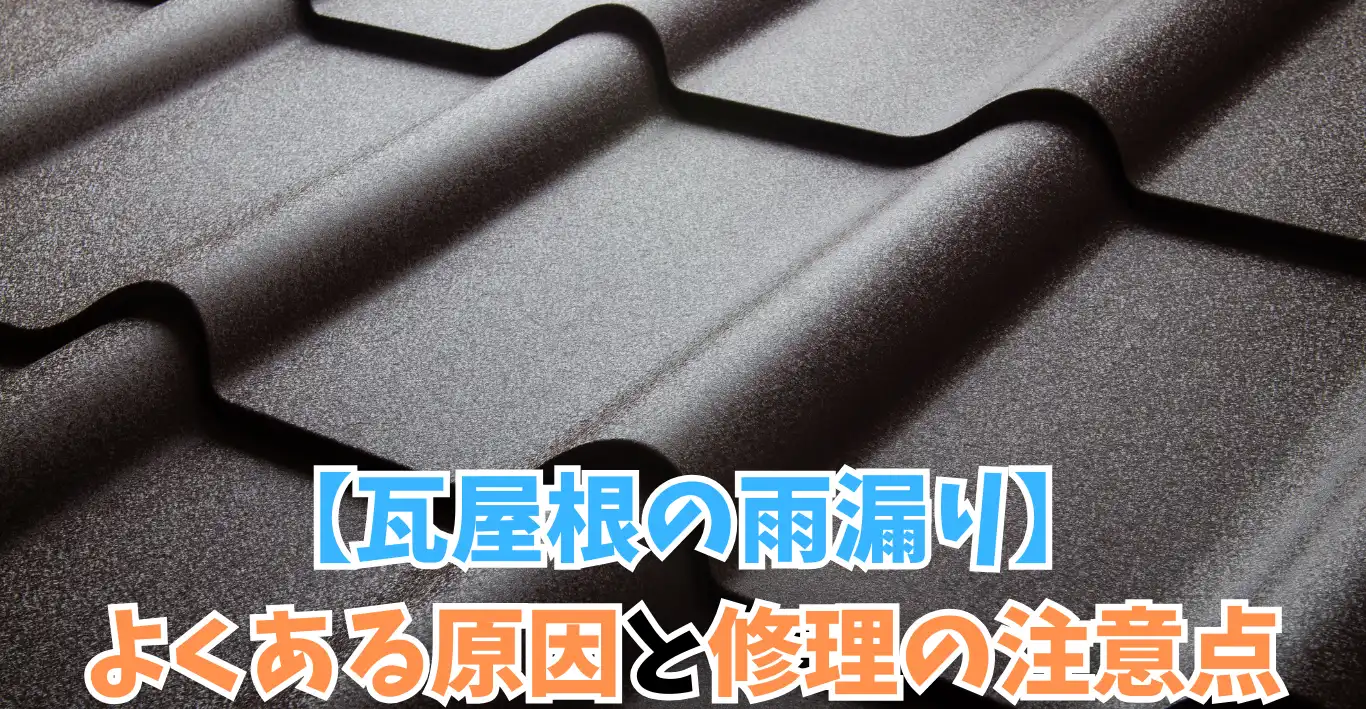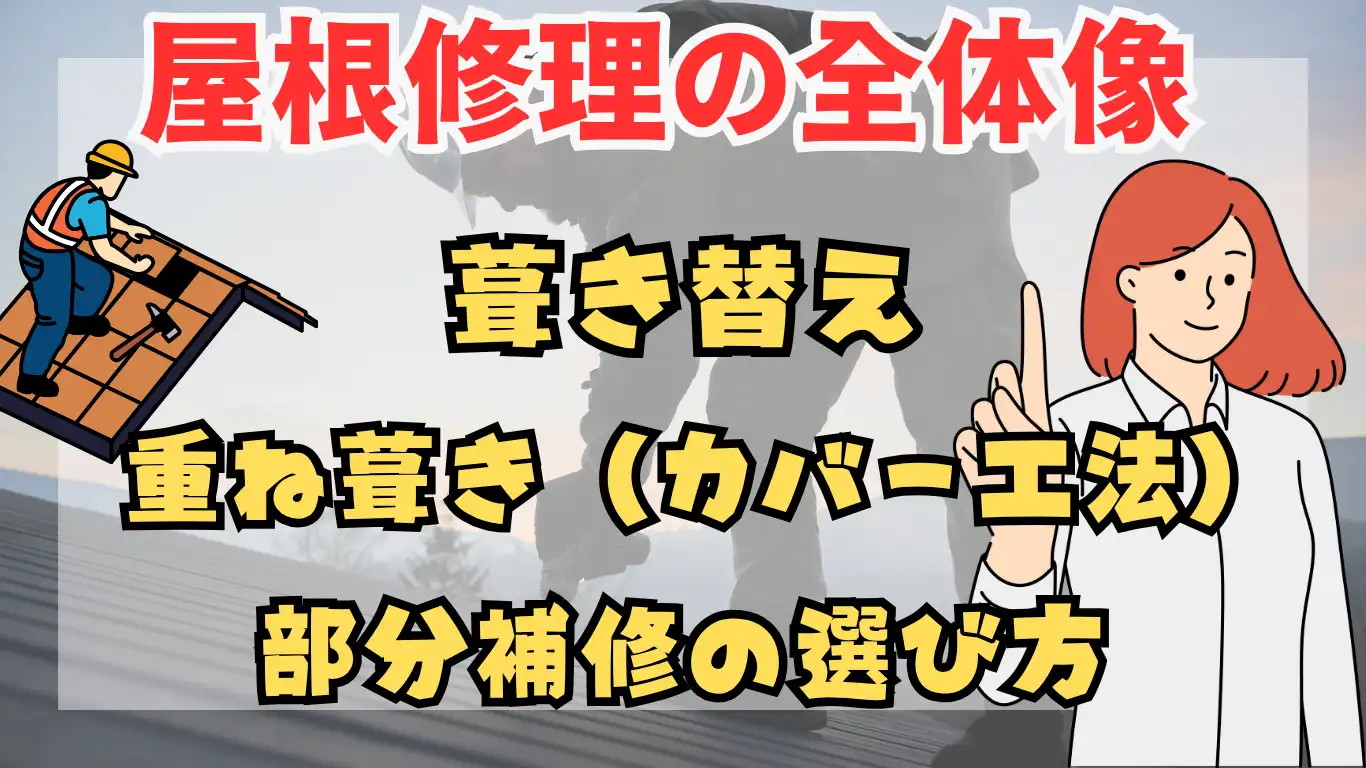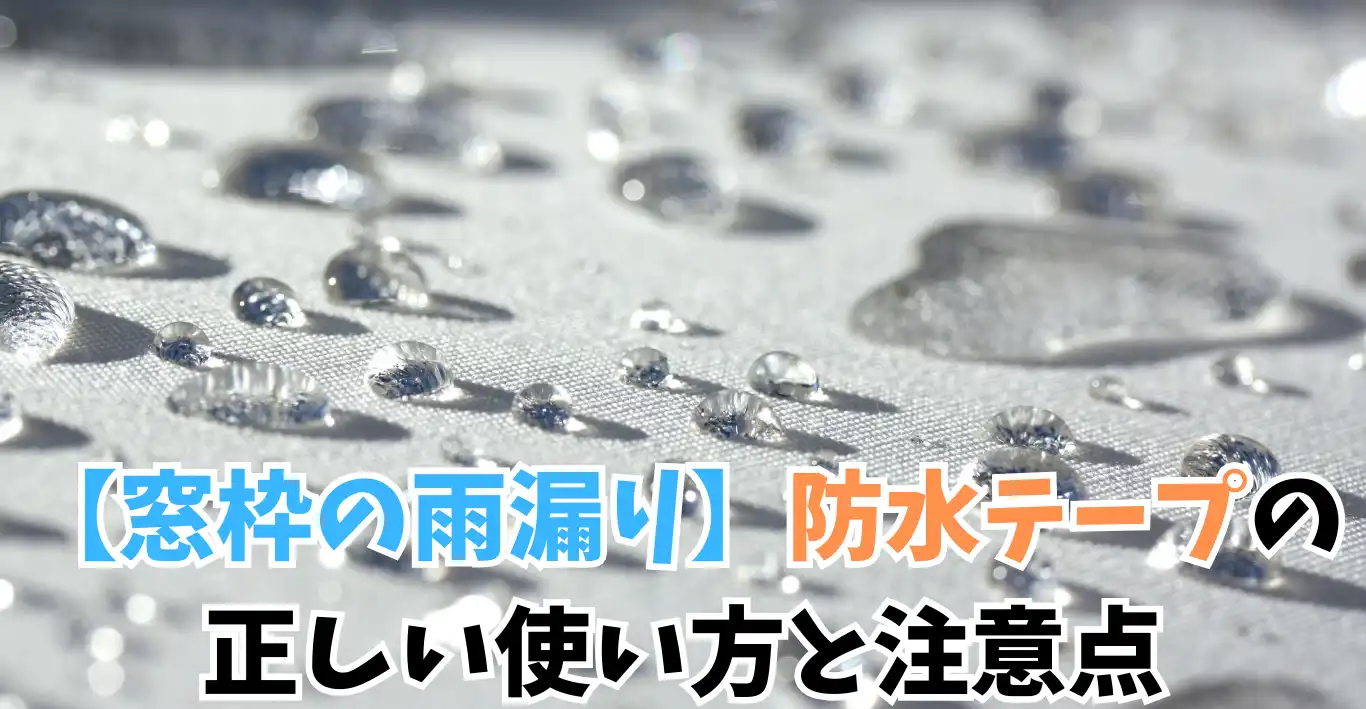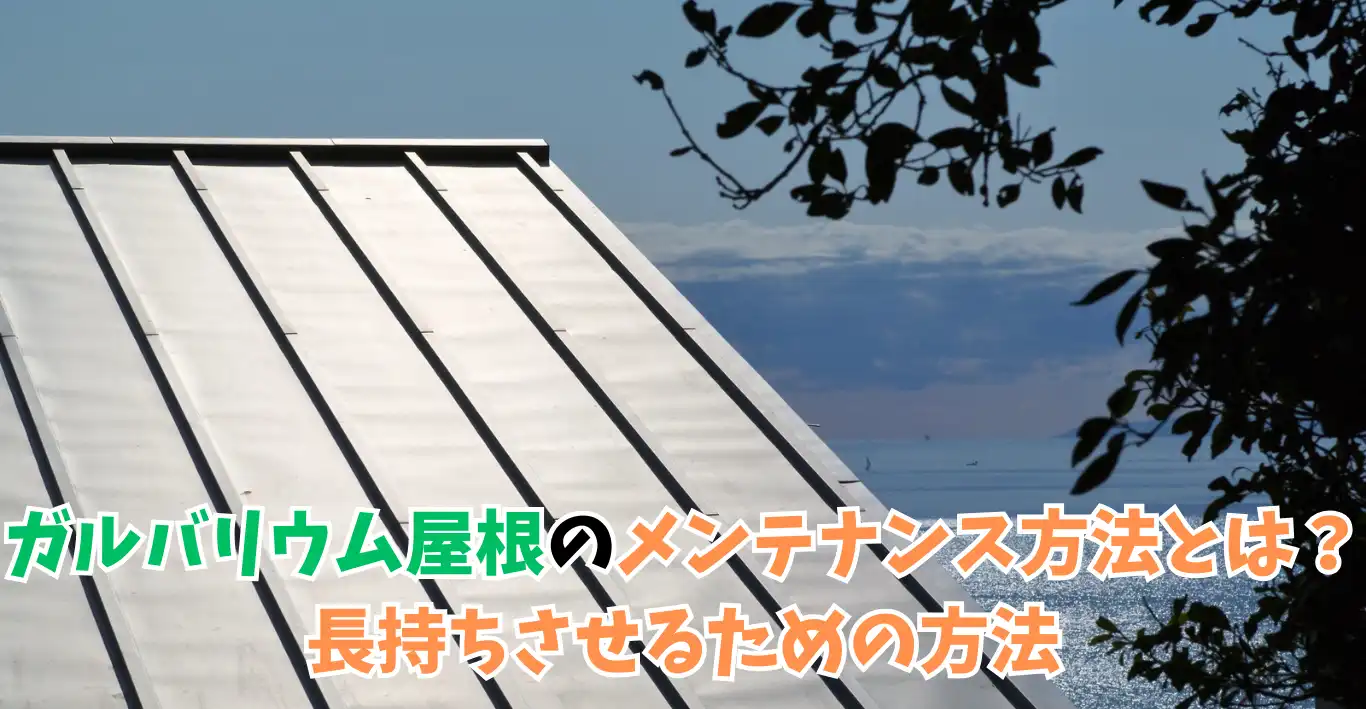陸屋根の防水改修は、建物の寿命を左右する重要工事です。
改修の成否は、既存の防水層の劣化状況を正確に診断し、水が溜まらないように排水計画と納まりを是正すること、そして屋上用途に合う最適な工法を選定することが成否を分けます。
特にウレタン、FRP、塩ビシートの主要三工法は、それぞれ特性が大きく異なるため、適切な工法選定が不可欠です。
陸屋根防水改修の考え方

陸屋根(フラットルーフ)は、勾配屋根とは異なり、屋根全体がほぼ水平な面であるため、防水層を設けることが必須となります。
ルーフバルコニーも建築基準法上は屋根の扱いであり、陸屋根の一形態です。
防水改修において最も重要なのは、水の浸入を防ぐ「止水」ではなく、水を確実に「排出」する排水計画と、防水層が途切れない連続性の確保です。
陸屋根防水の基本原則:水勾配と排水の確保
陸屋根は水平に見えますが、実際には雨水を排水口(ドレン)へと導くために、ごくゆるやかな傾斜(水勾配)が設けられています。
- ・水勾配不足のリスク:水勾配が不足していると、雨水が特定の場所に溜まり(水たまり)、防水層が常に水に浸された状態になります。この状態は、防水層の早期劣化や、防水性能の限界を超えた場合の雨漏り事故に直結します。
- ・ドレンの重要性:排水ドレン(排水口)は、陸屋根の面積から排水量を計算して口径や数量が設計されていますが、目皿(ストレーナー)の目詰まりや配管自体の閉塞により、設計通りの排出量を下回ることが少なくありません。改修工事の際には、既存の排水能力を低下させない配慮が不可欠です。
納まりと防水層の連続性
陸屋根の雨漏り事故は、平場(床面)からよりも、防水層の「端末」や「取り合い部」(特にパラペット、手すり壁の根元、設備貫通部)といった複雑な部位で多発します。
- ・立ち上がりの確保:バルコニーや陸屋根の防水層は、床面から250mm以上、かつ外壁の水切り上端部から50mm以上の立ち上がりを確保することが望ましいとされています。この立ち上がりが不十分だと、風雨の巻き込みや水が滞留した場合に、防水層の端部から水が回り込むリスクが高まります。
- ・異なる工種間の連携:バルコニーなどの防水層と外壁が取り合う部位は、施工業者の職種が異なり、構成部材も多いため、仕様が不明確になり雨漏りを招きやすい「落とし穴」です。防水層と外壁の透湿防水シート、水切りを連続させ、一体の止水ラインを形成することが、雨漏り予防の鍵となります。
劣化症状とリスク

防水層の劣化は、雨漏りだけでなく、建物躯体の腐食や構造的な安全性にも影響を及ぼすため、早期に症状を把握し対処することが重要です。
塗膜系防水(ウレタン、FRP)の劣化症状
- ・ふくれ(膨れ):既存の下地や防水層に含まれていた水分が、太陽熱により水蒸気となり、新しい防水層を押し上げて発生する現象です。ふくれを放置すると、防水層が破れてピンホール(小さな穴)が発生し、雨漏りの原因となります。
- ・ひび割れ(クラック):塗膜防水は、下地(モルタルやコンクリート)の動きや、木造住宅における下地の継ぎ目の動きに追従できず、ひび割れが生じることがあります。FRP防水では、下地の継ぎ目に沿って割れが生じることで、雨漏りのほとんどが引き起こされます。
- ・ピンホール:防水層に発生したごく小さな穴で、防水層の劣化や施工時のゴミ混入、硬化不良などが原因で生じます。ピンホールからの浸水は、下地を濡らし、腐食を進行させます。
シート系防水(塩ビシート)の劣化症状
- ・端末剥離(はく離):シート同士の重ね合わせ部分(ジョイント)や、立ち上がり部の端末が、経年や熱伸縮によって剥がれてしまうリスクがあります。シート防水は、この継ぎ目部分の処理が弱点とされています。
- ・シートの破れ:シートの表面劣化が進むと、歩行や外部からの衝撃によりシートが破断し、雨水の浸入経路となります。
排水周りの不良と水たまり
- ・ドレン周りの不良:排水ドレンは、雨水が集中する場所であるため、防水層の端末処理が複雑になり、劣化しやすい部位です。ドレン廻りからの浸水は、ルーフバルコニーからの雨水浸入ワースト8位に該当します。
- ・水たまり(水勾配不足):陸屋根の防水改修後に雨水が溜まりプール状態になり、塔屋出入り口の段差(立ち上がり)が低いことから雨漏りが発生した事例が報告されています。改修用ドレンの設置により、排水口の口径が小さくなり、排水機能が低下したことが原因となることもあります。
事前診断と調査手順
適切な改修工法を選定し、失敗を防ぐためには、現状の防水層や下地の劣化状況を正確に把握する事前診断と調査が不可欠です。
診断の基本原則とヒアリング
雨漏り診断の基本5原則に基づき、建物の構造、工法、築年数、修繕履歴(特に防水層の履歴)を正確に把握します。
- ・間診(ヒアリング)の徹底:入居者に対し、雨漏り発生箇所、時期、雨の強さや風向(風の強さや向き)との相関、漏水までのタイムラグなどを詳細に聞き取り、記録します。長雨や大雨、強風時にのみ発生する場合は、防水層や納まりに構造的な欠陥がある可能性を示唆します。
目視・含水測定による劣化状況把握
- ・目視調査:陸屋根の平場(床面)、立ち上がり部、ドレン周り、笠木、手すり根元、貫通部などの要点部位で、ふくれ、ひび割れ、剥離などの症状を確認します。
- ・含水測定と下地調査:塗膜防水の下地がコンクリートやモルタルの場合、水分計を用いて含水率を測定します。既存防水層の下地に多量の水分が残留している場合、密着工法を用いるとすぐにふくれが生じるリスクが高まります。下地の動きが原因で防水層にひび割れが生じている事例(FRP防水の事例など)では、下地の種類や固定状況(下地の留め付け不良)を確認することが重要です。
散水試験による浸入経路の特定
原因が特定できない複雑な雨漏りには、散水試験が不可欠です。
- ・再現性の確認:浸入が疑われる箇所に水をかけ、室内側で漏水が再現するかを確認します。散水試験の結果は、サーモグラフィーカメラを用いて温度差を可視化し、濡れた箇所を写真として明示することで、説得力のある報告書を作成できます。
- ・貫通部の散水:貫通部からの雨漏りの場合、断熱材を剥がして配管をむき出しにしてから、躯体と配管の隙間に散水し、浸入を確認します。
納まり要点の確認
特にトラブルが多い部位の納まり寸法をチェックします。
- ・立上り高さ:防水層の立ち上がりが床面から250mm以上、外壁水切り上端部から50mm以上あるか確認します。
- ・笠木・手すり根元:パラペットの笠木と手すり柱の取り合いは雨水浸入箇所ワースト2位となっており、3面交点での防水措置不良が雨漏りの原因となることが多いです。笠木や手すりの根元の防水処理(特に3面交点部のピンホール対策)を重点的に確認します。
工法比較の全体像
陸屋根防水の改修に用いられる主要な工法には、大きく「塗膜防水」であるウレタン防水とFRP防水、「シート防水」である塩ビシート防水があります。それぞれ構成、特性、適用条件が異なります。
| 工法 | 構成 | 長所 | 短所 | 適用条件・用途 |
|---|---|---|---|---|
| ウレタン防水 | ウレタンゴム系塗膜材を塗布し、塗膜層を形成。保護層(トップコート)が必要。密着工法と通気緩衝工法がある。 | 継ぎ目がない(シームレス)。複雑な形状に対応しやすい。比較的安価。 | 施工に手間がかかり工期が長くなる。下地の影響(水分、動き)を受けやすい。 | RC造、S造、木造。改修時に多用。歩行頻度の低い屋上、バルコニー。 |
| FRP防水 | 防水用ガラスマットとポリエステル樹脂の積層による塗膜防水。 | 非常に強固で継ぎ目がない。短工期での施工が可能。歩行に適している。 | 下地への追従性が低い。下地の動きや継ぎ目で割れが生じやすい。 | 木造住宅のバルコニーに最も多く施工されている。常時歩行(ルーフバルコニー)用途。 |
| 塩ビシート防水 | 塩化ビニル樹脂系シートを下地に接着または固定。接着工法と機械的固定工法がある。 | 下地の影響を受けにくい(機械的固定工法)。耐久性が高い。 | シートの重ね合わせ部分(ジョイント)が剥がれるリスクがある。複雑な部位への施工が難しい。 | RC造、S造。大規模な屋上。既存層が水分を含んでいる改修時(機械固定工法)。 |
- ・下地との相性:ウレタン防水とFRP防水は下地に密着させるため、下地に含まれる水分や動きに弱いです。既存下地の含水が多い場合は、通気緩衝工法(ウレタン)または機械的固定工法(塩ビシート)を選定することで、下地の影響を回避できます。
- ・使用条件(歩行):FRP防水は強固な防水面となるため、木造住宅のバルコニーなど、小面積で歩行に適した防水層として多用されています。ウレタン防水も歩行が可能ですが、FRPほどの強度はありません。
ウレタン防水(密着・通気緩衝)
ウレタン塗膜防水は、改修工事で最も多く採用される工法の一つです。既存下地の種類を選ばず施工できる汎用性の高さが特徴です。
密着工法と通気緩衝工法の違い
- ・密着工法:ウレタン塗膜材を下地に直接塗布して密着させる工法です。下地が健全で水分を含んでいない場合に適用されます。
- ・通気緩衝工法:下地に通気緩衝シートを敷き、その上からウレタン防水層を形成する工法です。既存の下地(特にRC造やS造)が水分を含んでいる場合、この水分を防水層のふくれの原因にしないよう、シートと塗膜の間に通気層を設け、脱気筒を通じて外部へ水分を排出させます。改修工事では、既存の防水層を撤去せずに施工できるため、この通気緩衝工法が一般的に採用されます。
施工における品質管理の要点
- 1. 下地調整とプライマー塗布:既存の下地が健全でないと、塗膜にひび割れや剥離が生じるため、下地の清掃、ひび割れ補修、ケレン処理などを十分に行います。その後、下地と防水材の密着性を高めるためにプライマーを塗布します。
- 2. 層厚設計:ウレタン防水の品質は、定められた膜厚を確保することに依存します。液状の材料であるため、職人の技量によって膜厚にバラつきが出やすいことが課題です。膜厚計を用いて、設計通りの厚さが確保されているかを検査する必要があります。
- 3. 脱気筒の設置:通気緩衝工法を採用した場合、通気層内の水蒸気を外部に排出するために脱気筒を適切に設置します。脱気筒の設置箇所は、水分の溜まりやすい箇所や、既存防水層の劣化がひどい箇所を中心に計画します。
FRP防水
FRP防水は、強度が高く、硬化が速いという特徴から、主に木造住宅のルーフバルコニー防水に多用されています。
適用範囲と歩行用途の適性
FRP防水は、ガラス繊維などの強化材で補強されたプラスチックであり、防水層に継ぎ目がない強固な防水面を形成するため、歩行に適していることが最大のメリットです。短工期での施工が可能であるため、工期を長く取れない現場にも適しています。
下地との相性とひび割れリスク
FRP防水は強固である反面、柔軟性が低く、下地の動きへの追従性が低いという特性があります。
- ・ひび割れの原因:木造住宅のバルコニーや陸屋根でFRP防水が雨漏りを起こす原因のほとんどは、下地の継ぎ目に沿って防水層に割れが生じることです。これは、下地の留め付け不良(78%)が主な施工不良の内容であり、下地がたわむことによって割れが発生します。
- ・下地補修の重要性:FRP防水を採用する場合、下地のたわみを防ぐための補強や、下地材同士の固定(留め付け)を確実に行うことが、ひび割れ発生を防ぐために最も重要です。
紫外線対策(トップコート)
FRP防水層は紫外線に弱いため、必ず紫外線から保護するためのトップコート(保護塗料)を塗布する必要があります。トップコートが劣化すると、FRP層自体が早期に劣化し、防水性能を失うため、定期的なトップコートの塗り替え(5年〜10年程度が目安)が必要となります。
塩ビシート防水(機械固定/接着)
塩ビシート防水は、シートを物理的に固定または接着する工法であり、特に大規模な屋上や、既存の下地処理が難しい改修工事に適しています。
機械的固定工法と接着工法の選択
- ・機械的固定工法:下地に専用アンカーで固定ディスクを設置し、そのディスクに防水シートを接着(溶着)させて張っていく工法です。シートを全面接着しないため、下地の影響を受けにくいという特徴があり、「浮かし張り」「絶縁工法」とも呼ばれています。既存の防水層(アスファルトなど)が水分を含んでいる場合でも、そのまま施工できるため、改修工事では一般的です。
- ・接着工法:下地に接着剤を塗布し、シートを貼り付ける工法です。下地の含水率が低い場合に適していますが、下地が動いたり、内部の水分が水蒸気となった場合に、シートにふくれが生じるリスクがあります。
端末・継手処理の重要性
シート防水の弱点は、シート同士の張り合わせ部分(ジョイント)が経年によって剥がれるリスクがあることです。
- ・溶着の品質管理:シートの重ね代は、熱風溶着や誘導加熱(IH)などの特殊な技術を用いて、シート同士を確実に一体化させます。この溶着部分の品質が防水性能を左右するため、施工後の検査(剥離抵抗試験など)が重要となります。
- ・端末処理:複雑な形状の部位(入隅・出隅、貫通部)への施工が塗膜防水に比べて難しいというデメリットがあります。これらの部位では、専用の成形役物やシーリング材を併用し、シートの端末部から水が浸入しないよう、納まりのディテールに細心の注意を払う必要があります。
耐風性能の考え方
シート防水は風の影響を受けやすいため、特に高層建築や沿岸強風地域では、風圧に耐えられるよう固定方法を設計する必要があります。機械的固定工法の場合、固定ディスクのピッチや間隔を調整することで、耐風圧性能を確保します。
納まり要点

陸屋根防水改修の成功は、平場よりも、防水層の連続性が途切れやすい「納まり部」のディテールに依存します。
立上り高さとパラペット処理
- ・立上りの必須寸法:防水層の立ち上がりは、床面から250mm以上、かつ外壁の水切り上端部から50mm以上の高さが必要です。これにより、外壁側の透湿防水シートとの重ね代も90mm以上確保できるとされています。
- ・パラペットの対策:陸屋根の笠木は、手すり壁(パラペット)の上端に取り付けられますが、笠木と外壁の取り合い部から雨水が浸入する事故例が報告されています。笠木下部の通気口からの雨水浸入を防ぐため、笠木とサイディングの隙間寸法を10mm程度にし、防雨効果のある換気部材を取り付けることが予防策として挙げられています。
排水口(改修ドレン、オーバーフロー)の設計
- ・改修ドレンの必須性:改修工事では、既存ドレンの不具合からの雨漏りを防ぐため、改修用ドレンの設置が必須とされています。これは既存ドレンの内側に設置され、新規防水層と一体化させることで雨漏りを防ぎます。
- ・排水機能の維持:改修用ドレンは口径が小さくなる(例:100φが90φ程度)ため、元の排水能力に余裕がない場合、満水による雨漏りの危険性が高まります。必要に応じて、ドレンの点検・清掃をこまめに行い、排水機能を維持することが重要です。
- ・オーバーフロー(非常用排水):排水ドレンが詰まった際の満水状態に備え、防水層の立ち上がり高さより低い位置にオーバーフロー(非常用排水口)を設けることで、雨水の貯水許容量(逃げ道)を確保しておくことが、雨漏りリスク低減のために重要です。
貫通部と入隅・出隅の処理
- ・設備貫通部:給水管や配管などの貫通部は、躯体に穴を開けるため、最も雨水が浸入しやすい部位の一つです。躯体と配管の隙間をしっかりとシーリングで埋め、防水層を筒状に巻き上げて施工します。
- ・入隅・出隅(コーナー):笠木と手すり柱の取り合いのような3面交点は、二次防水の措置不良によるピンホールができやすい部位であり、雨水浸入箇所ワースト6位を占めています。入隅・出隅では、防水層に力が集中しやすいため、増し塗りや増し貼りを行い、防水層を補強します。
断熱の有無と通気
陸屋根防水改修時に断熱層を設けるかどうかは、建物の省エネルギー性能や、防水層の耐久性に大きく関わります。
断熱工法と防水層の構成
陸屋根の断熱工法には、大きく非断熱(防水層のみ)と断熱工法があります。
- ・非断熱工法:コンクリートスラブや下地に直接防水層を形成します。
-
・断熱工法:断熱材を組み込むことで、屋上からの熱の出入りを防ぎ、室内の省エネ性能を高めるとともに、下地の温度変化を抑え、防水層の熱伸縮による劣化を抑制する効果が期待できます。
・保護断熱工法(外断熱):防水層の上(外側)に断熱材を敷き、その上に保護層(砂利やタイルなど)を設ける工法です。防水層が熱や紫外線から保護されるため、耐久性が向上しやすいという利点があります。
・内断熱工法:下地(スラブ)の内側(室内側)に断熱材を設ける工法です。防水層が外気の影響を直接受けるため、防水層自体の温度変化による伸縮は大きくなります。
熱伸縮と不具合の関係
陸屋根は日射の影響を強く受け、特に夏場には防水層の表面温度が高温になります。
- ・熱伸縮によるひび割れ:塗膜防水(特にFRP)は、下地の熱伸縮による動きに追従できず、ひび割れが発生するリスクがあります。断熱層を適切に設けることで、下地および防水層の温度変化を緩和し、熱伸縮による不具合発生のリスクを低減させることができます。
通気と結露対策
下地に水分が残留している場合、密着工法を避けるか、ウレタンの通気緩衝工法や塩ビシートの機械的固定工法を採用することで、防水層のふくれを防ぎます。通気緩衝工法では、内部の湿気を脱気筒から排出することで、結露や内部の腐食リスクを低減します。
工期・費用レンジと段取り

陸屋根防水改修の費用と工期は、工法の選択、面積、下地の状態、そして必須となる乾燥・硬化時間によって大きく変動します。
費用レンジ(一般的目安)
防水改修費用は、工法や既存下地の処理、立ち上がり部の複雑さ、断熱層の有無によって坪単価が大きく変動します。
| 工事内容 | 費用目安(税別・坪単価) | 備考 |
|---|---|---|
| ウレタン防水(密着工法) | 1.5万~3万円/坪 | 下地が健全で含水がない場合。 |
| ウレタン防水(通気緩衝工法) | 2万~4万円/坪 | 既存防水層の上からの改修に一般的。脱気筒、通気シート含む。 |
| FRP防水(木造バルコニー) | 2万~4万円/坪 | 下地補修や笠木交換は別途。歩行に適する。 |
| 塩ビシート防水(機械固定工法) | 2.5万~4.5万円/坪 | 大面積、既存層の含水がある場合に適する。 |
| 下地調整・撤去費 | 5千円~2万円/坪 | 既存層撤去、水勾配調整モルタル施工など。 |
| 改修ドレン・役物設置費 | 5万~20万円/式 | 排水口の数や立ち上がり部の長さによる。 |
| 仮設費用(足場) | 600~900円/m² | 中低層建築の場合、屋上以外に足場が必要な場合がある[指定費用]。 |
注:これはあくまで一般的な目安です。築43年のRC造ビルの大規模防水改修事例では、内装復旧費を含めずに数百万〜1000万円を超える可能性があります。
工期レンジと段取り
工期は、塗膜防水(ウレタン、FRP)の場合、材料の乾燥・硬化時間が必要なため、気象条件に大きく左右されます。
- ・ウレタン防水:50m²程度の標準的な面積の場合、5日〜10日程度が目安です。ウレタン材の層間やトップコートの乾燥・硬化時間(夏場は短縮、冬場は延長)を厳守する必要があります。
- ・FRP防水:硬化が速いため、短工期での施工が可能で、2日〜4日程度が目安です。
- ・塩ビシート防水(機械固定):シートを固定し溶着するため、塗膜防水ほどの乾燥時間は不要ですが、シートの敷設や端末処理に時間を要します。5日〜10日程度が目安です。
気象リスクと段取り
塗装・防水工事は、天候に左右されやすいです。
- ・施工不可条件:気温5℃以下、湿度85%以上、または降雨、強風時は施工が不適とされることが一般的です。特に塗膜防水は、雨や露にあたると品質が低下するため、硬化前の降雨は厳禁です。
- ・事前の段取り:工事期間中は、天候の急変に備え、防水層が濡れないよう養生ネットやシートで保護する段取りが重要です。
品質管理と検査
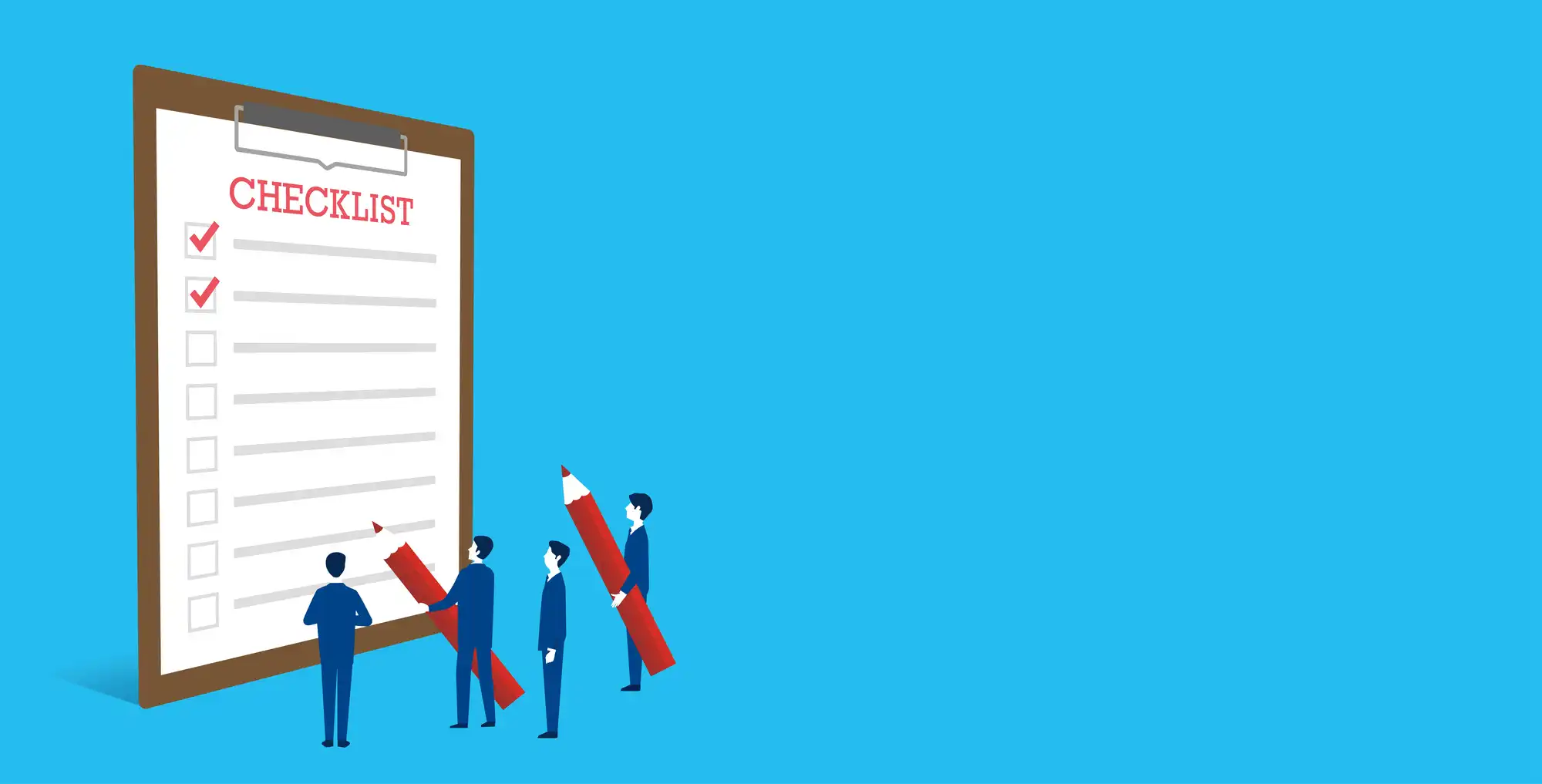
陸屋根防水改修の品質を確保するためには、施工中の厳格な管理と、完了後の検査が不可欠です。
施工中の品質管理と記録
- ・写真台帳の作成:施工前、下地調整、プライマー塗布、防水層の積層(膜厚)、端末・立上り処理、改修ドレン設置、トップコート完了など、各工程を詳細に写真で記録します。これにより、目に見えない部分の施工品質を証明できます。
- ・膜厚・付着検査:ウレタン防水では、規定の膜厚が確保されているか、膜厚計で検査します。FRP防水では、積層数や樹脂の塗布量が規定通りか、付着強度を確保できているかを確認します。
完了後の検査
- ・通水(散水)確認:改修工事完了後、再度散水試験を実施し、雨漏りが完全に解決していることを確認することが重要です。これは、仮説の修理確認と、他の浸入経路が排除されたことの実証となります。
保証の範囲と条件
- ・防水保証期間:陸屋根防水の保証期間は、工法や材料のグレードによって異なりますが、一般的には10年〜15年程度が目安です。
- ・瑕疵担保責任:住宅事業者は、引き渡しから10年間、構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分(防水層含む)について瑕疵担保責任を負います。この保証内容は、国土交通大臣の定めた設計施工基準を満たすことが条件となります。
- ・保証の免責事項:雨漏り・漏水・結露水などに起因するシロアリ被害は、通常防蟻処理の保証期間内であっても免責となる場合があるため、防水層の欠陥は早期に発見し対処することが重要です。
よくある失敗と回避策

陸屋根防水改修における失敗は、多くの場合、事前の診断不足や、水の流れを無視した施工ディテールに起因します。
勾配不足の放置
- ・失敗例:既存の陸屋根に水勾配が不足し、水たまりがあるにもかかわらず、勾配調整を行わずにそのまま防水層を重ねて施工してしまう。
- ・回避策:事前診断で水たまりを確認した場合、モルタルなどを用いて水勾配を是正する下地調整(勾配調整)を必ず行い、雨水を確実にドレンへ流す計画を立てます。勾配不足が原因で防水改修後に雨漏りが再発した事例も報告されています。
端末のシーリング依存
- ・失敗例:笠木や手すり根元、入隅・出隅などの防水層の端末処理を、防水材の重ね貼りや立ち上げではなく、安易にシーリング材のみに頼ってしまう。
- ・回避策:シーリング材は経年劣化するため、防水の主たる機能を持たせてはなりません。パラペットと外壁の取り合いなどでは、防水層の立ち上がり(床面から250mm以上)や、防水シートと水切りの連続性を確保する構造的な防水処理を優先します。笠木廻りでは、3面交点の防水措置不良が雨漏りの原因の57%を占めており、防水層を一枚の防水紙でピンホールができないように処理するなどの対策が必要です。
排水計画の不備と改修ドレンの口径縮小
- ・失敗例:改修工事時に改修用ドレンを設置したことで、既存のドレン口径が縮小し、排水能力が不足して満水によるオーバーフローが発生する。
- ・回避策:既存の排水能力を評価し、必要に応じてドレンの増設や、オーバーフロー(非常用排水口)を設置するなど、排水計画を再検討します。日常的なドレンの点検と清掃も重要です。
既存層の含水放置
- ・失敗例:既存の下地(モルタルなど)に多量の水分が残留しているにもかかわらず、密着性の高いウレタン防水の密着工法やFRP防水を採用し、すぐに防水層にふくれや剥離が発生する。
- ・回避策:事前診断で含水率が高いと判断された場合は、下地の水分を外部に排出できる通気緩衝工法(ウレタン)または機械的固定工法(塩ビシート)を選定します。
業者選び・FAQ・まとめ

陸屋根防水改修は、専門性が高い工事であり、業者選びが成功の鍵となります。
業者選びのポイント
- 1. 診断能力と技術:雨漏り診断士などの資格を持ち、散水試験やサーモグラフィーカメラを用いて原因を正確に特定し、防水層の納まり(立上り、ドレンなど)に関する専門知識を持っている業者を選びます。
- 2. 仕様書の明確性:「防水層の立ち上がり寸法」「使用材料(グレード)」「膜厚」「下地調整の具体的な手順」などが明確に記載された仕様書と工程表を提出できるか確認します。一般的な材料名だけでなく、具体的な部位ごとの標準仕様書や施工上の注意点、材料名や寸法が明記されている必要があります。
- 3. 保証とアフターフォロー:施工後の保証期間(10年〜15年目安)と、保証内容(免責事項を含む)を明確に確認します。
FAQ(よくある質問と回答)
Q1. 陸屋根の防水層の寿命はどのくらいですか?
A. 防水層の種類やグレード、設置環境(日射、風雨)によって異なりますが、一般的には10年〜15年程度が目安とされています。ただし、FRP防水のトップコート(紫外線保護層)は、これより短い周期(5年〜10年程度)での塗り替えが必要となる場合があります。改修時期はあくまで目安であり、ふくれ、ひび割れ、端末の剥離などの劣化症状が見られたら、すぐに専門家による点検が必要です。
Q2. ウレタン防水の「密着工法」と「通気緩衝工法」はどのように選ぶべきですか?
A. 密着工法は、既存の下地が健全で水分を含んでいない場合に適しています。一方、通気緩衝工法は、既存の下地や防水層に水分が残留している可能性が高い場合や、既存防水層の撤去が難しい改修時に適しています。通気緩衝工法は、防水層の下に敷く通気緩衝シートと脱気筒により、水蒸気を外部に排出し、新しい防水層のふくれを防ぐ効果があります。
Q3. 陸屋根の防水層は床面から何mm以上立ち上げる必要がありますか?
A. 陸屋根やバルコニーの防水層は、万が一排水が滞留した場合に雨水が躯体内に浸入するのを防ぐため、床面から250mm以上立ち上げることが望ましいとされています。これは、外壁側の透湿防水シートとの重なり代を確保し、一体の止水ラインを形成するためにも重要な寸法です。
Q4. FRP防水は強度が高いと聞きますが、ひび割れやすいのはなぜですか?
A. FRP防水は、塗膜自体が非常に強固で硬い(剛性が高い)ため、下地(モルタルや木造下地)が地震や構造的な動きでたわんだ際、その動きに追従できず、下地の継ぎ目に沿って割れが発生しやすいという特性があります。FRP防水の雨漏りの原因のほとんどは、下地材の留め付け不良(78%)による割れが原因です。歩行に適していますが、下地の補強や適切な緩衝処理が必要です。
Q5. 防水改修工事後に水たまりができた場合の対処法は?
A. 防水改修後に水たまりができるのは、既存の水勾配不足が原因であることがほとんどです。水たまりを放置すると防水層の劣化を早めるため、専門業者に依頼し、モルタルなどを用いて水勾配を是正する再改修が必要です。また、排水ドレンの目詰まりによる満水状態が原因の場合もあるため、こまめな点検と清掃、および非常時のオーバーフロー(非常用排水口)の設置も検討すべきです。
まとめチェックリスト
- 1. 水勾配と排水計画:水たまりがないか確認し、あれば勾配是正を含めた排水計画(改修ドレン、オーバーフローの設置)を立てていますか?
- 2. 事前診断:散水試験や含水計を用いて、雨漏りの浸入経路と下地の含水状態を正確に特定しましたか?
- 3. 工法選定:建物の用途(歩行頻度)と下地の状態(含水、動き)に合った最適な防水工法(ウレタン、FRP、塩ビシート)を選定しましたか?
- 4. 納まりの確認:防水層の立ち上がり寸法(床面から250mm以上)や、パラペット笠木、貫通部の端末処理が構造的に適切に設計されていますか?
- 5. 通気緩衝工法の適用:既存の下地に水分が残留している場合、ウレタンの通気緩衝工法や塩ビシートの機械固定工法を採用し、ふくれを防止する対策を講じましたか?
- 6. 品質管理:施工中の写真台帳作成、膜厚検査、そして完了後の通水確認 を行う計画になっていますか?