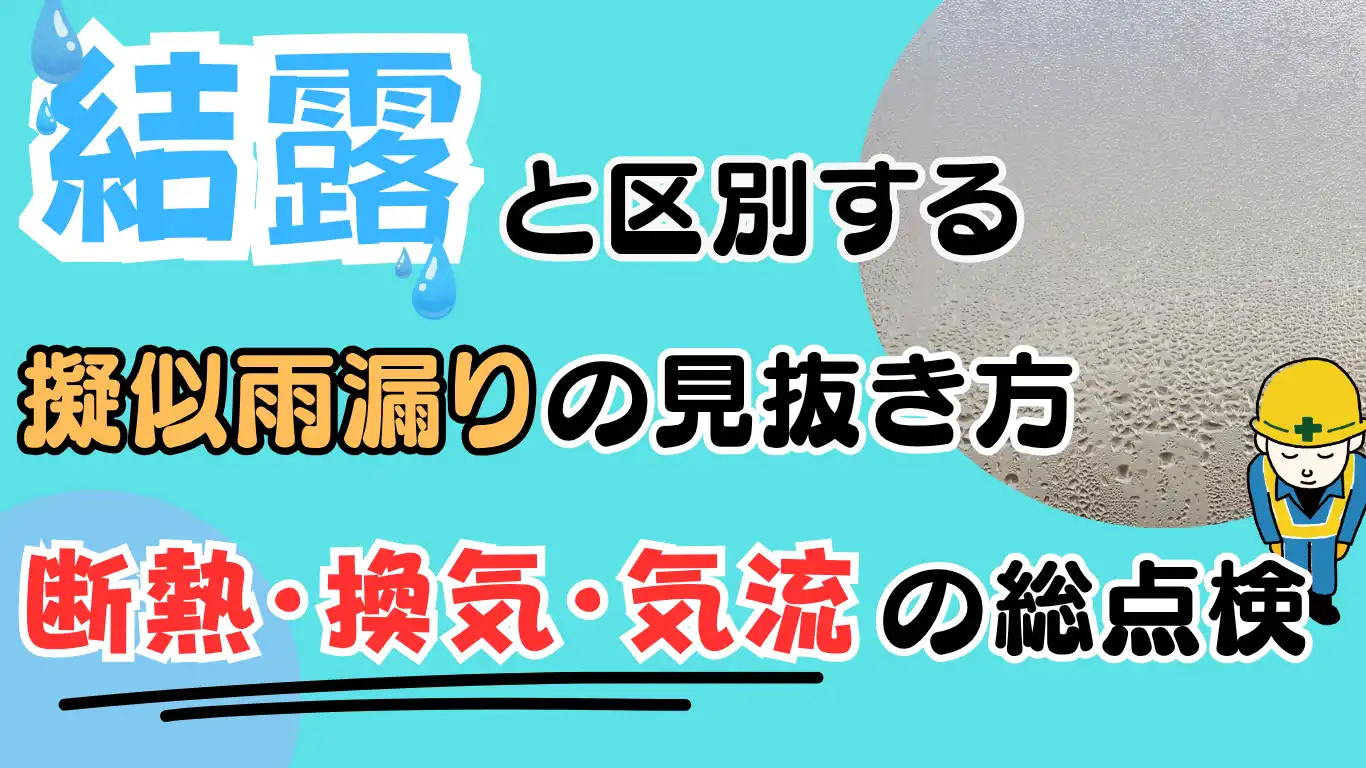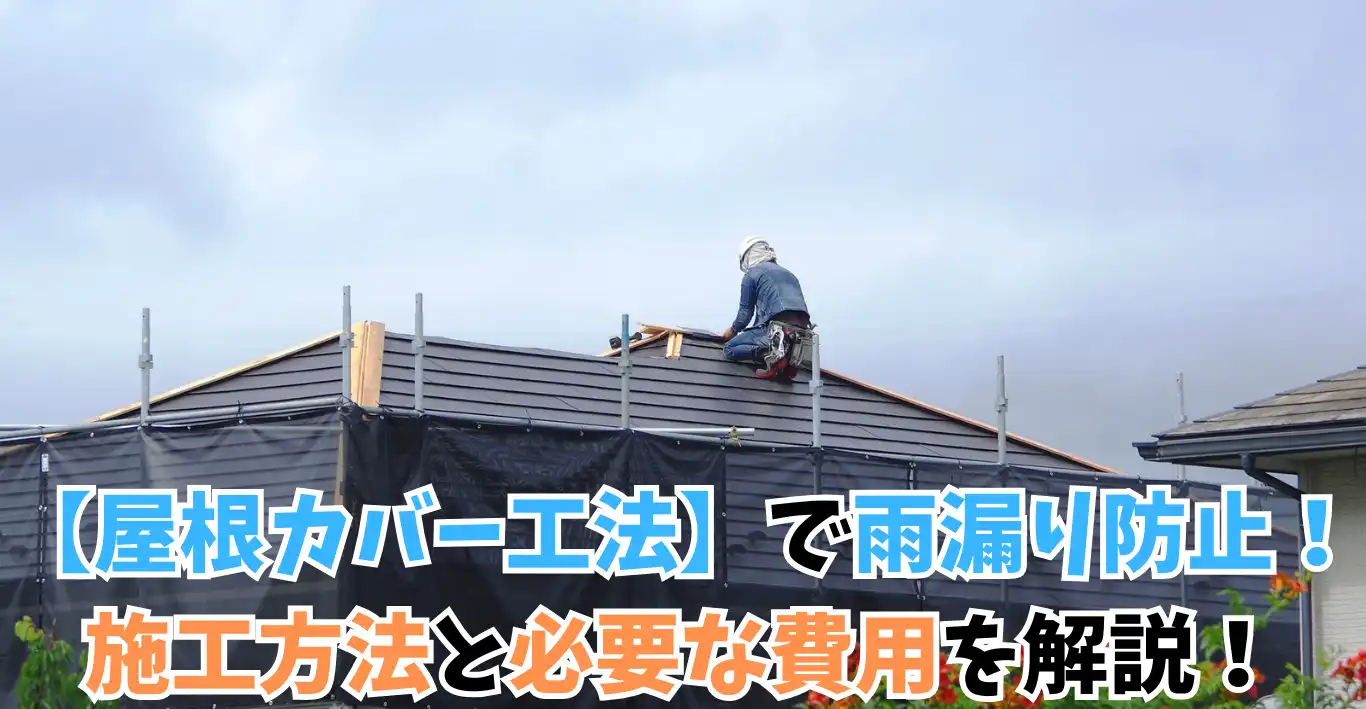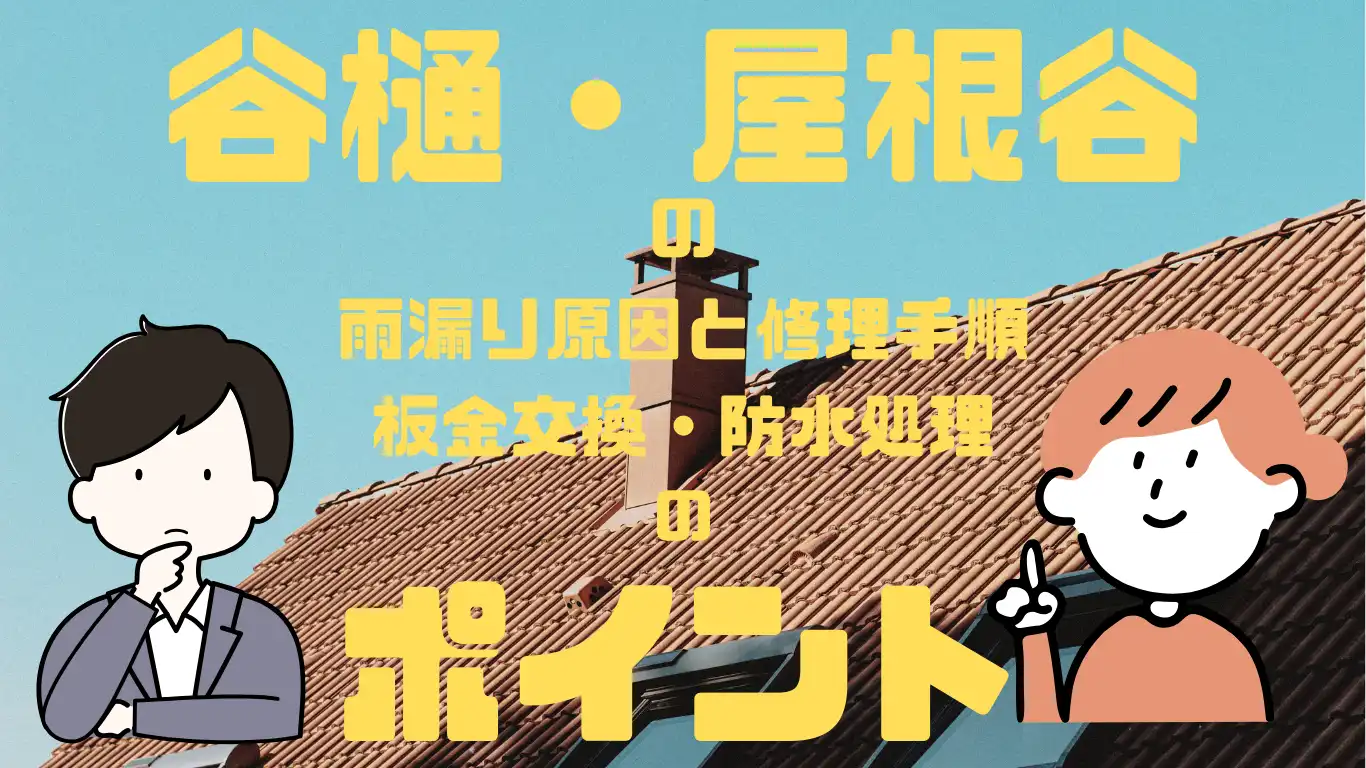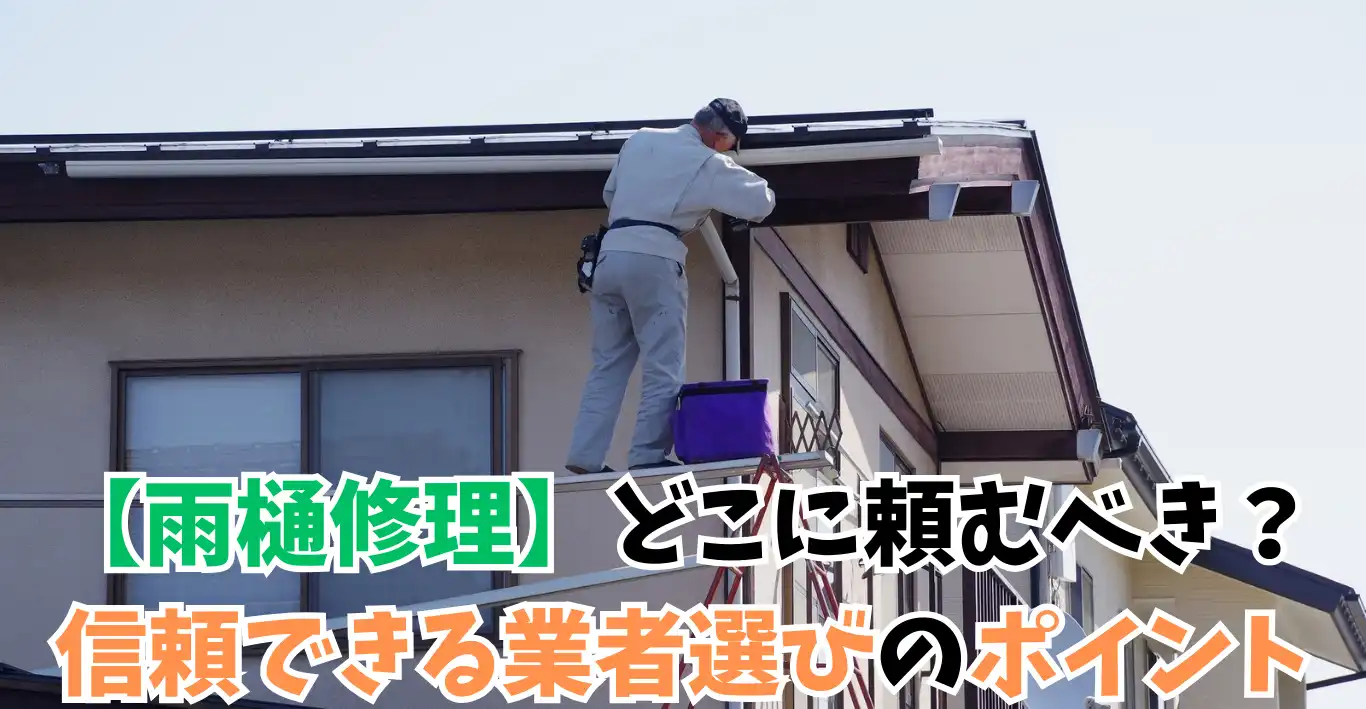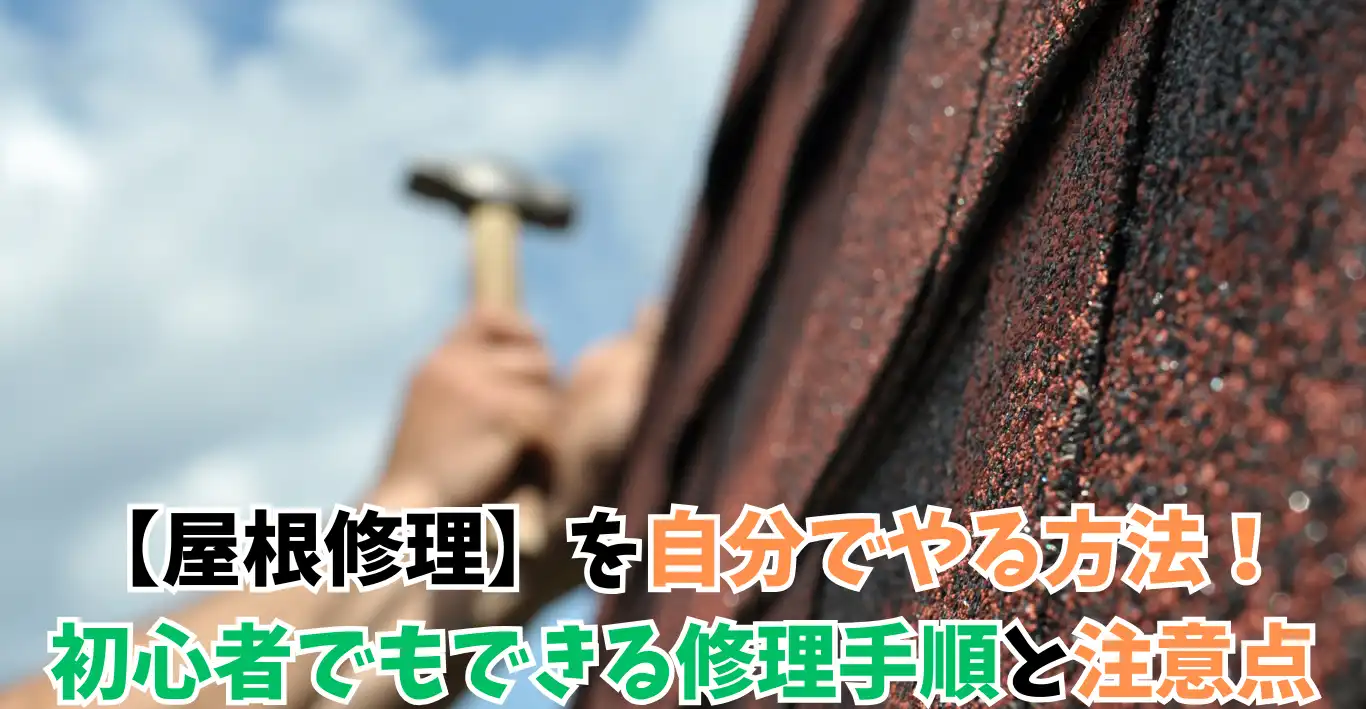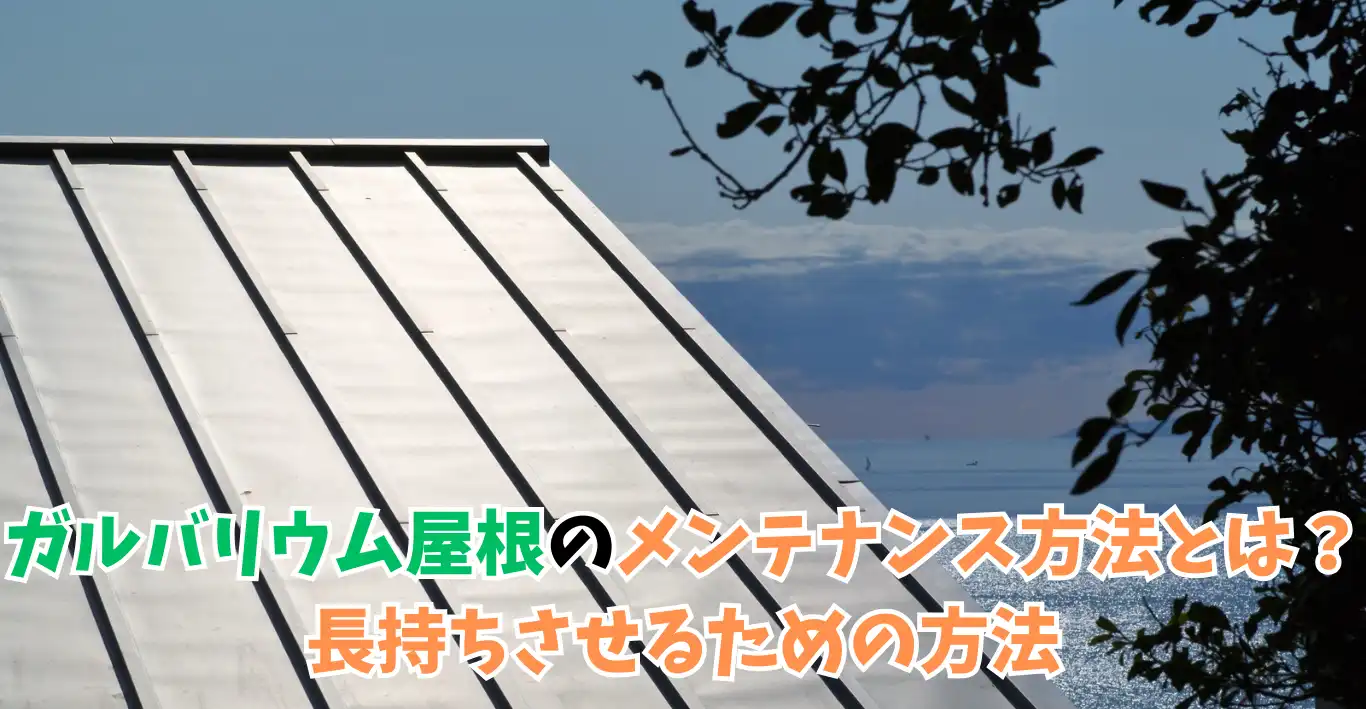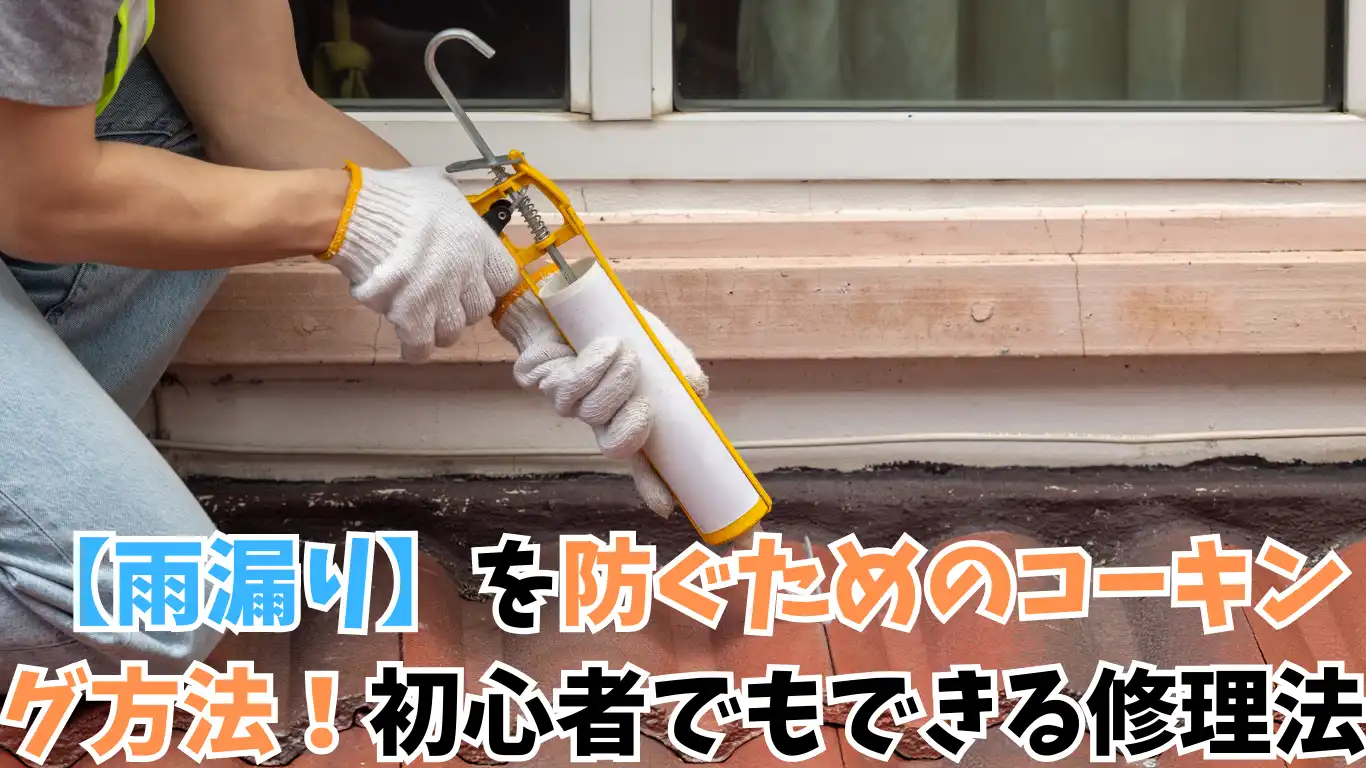天井や壁に水滴やシミが発生し、それが雨漏りなのか結露なのか判断に迷う現象を擬似雨漏りと呼びます。
擬似雨漏りを確実に解決する鍵は、“発湿×表面温度×気流”の三点管理に基づき、結露の発生メカニズムを理解し、断熱・気密・換気の構造的欠陥を是正することです。
雨漏りではないからといって放置すると、建物躯体の腐朽や健康被害を招くため、早期の原因特定が求められます。
擬似雨漏りとは何か—雨漏りとの違いと放置リスク
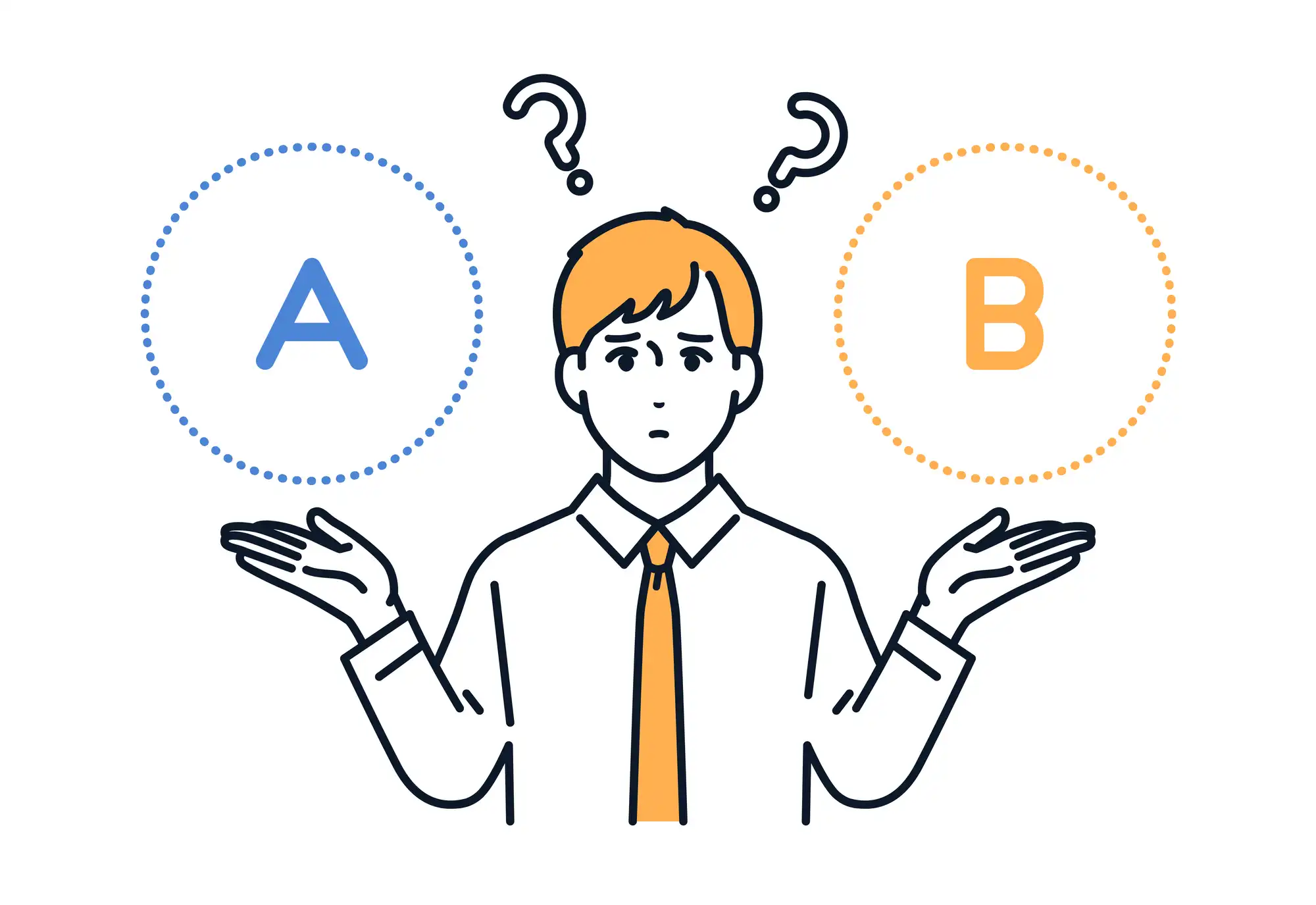
擬似雨漏りとは、建物の外部からの水の浸入(雨漏り)ではなく、主に室内で発生した水蒸気が、壁内や天井裏の冷たい部材に触れて結露となり、それが水滴となって浸出することで、あたかも雨漏りのように見える現象を指します。
雨漏り(浸水)と結露(凝縮水)の違い
- ・雨漏り(浸水):建物外部の防水層(屋根材、ルーフィング、外壁材など)の欠損や施工不良により、雨水が外部から内部に浸入する現象です。強風時や大雨時など、特定の天候条件下で発生する傾向があります。浸出水は、屋根材や下地の汚れを含んで着色している場合があります。
- ・結露(擬似雨漏り):室内外の温度差と高い室内湿度が原因で、空気中の水蒸気が凝結して液化する現象です。雨が降っていなくても、特に冬季の暖房使用時や梅雨時など、室内外の温湿度のバランスが崩れた際に発生します。
結露放置が招く深刻なリスク
天井裏や壁内で発生した結露水を放置すると、深刻な二次被害を招きます。
- 1. 構造材の腐朽:結露水により木材(野地板、垂木、柱、間柱など)が常に濡れた状態になると、木材の腐食(腐朽)が進行します。腐朽は建物の構造的な安全性を低下させます。
- 2. シロアリ被害:濡れた木材はシロアリの被害を受けやすくなります。腐朽とシロアリ被害は、建物の寿命を縮める大きな要因です。
- 3. カビの発生と健康影響:湿気の多い環境では、カビが発生しやすくなります。カビは建材の劣化を早めるだけでなく、アレルギーや呼吸器系疾患の原因となる可能性があります。
- 4. 断熱性能の低下:断熱材(グラスウールなど)が結露水を含んで湿ってしまうと、本来の断熱性能が著しく低下します。
仕組みの基礎
結露(擬似雨漏り)は、建築物理の基本である温度、湿度、空気の流れが不適切に管理された結果として生じます。
露点と結露のメカニズム
空気中に含まれる水蒸気が凝結して水滴に変わる温度を露点温度と呼びます。
- ・結露の発生条件:結露は、水蒸気を含んだ空気が、その空気の露点温度以下の表面温度を持つ部材(ガラス、壁、屋根下地など)に触れたときに発生します。
- ・相対湿度(RH):室内湿度が高いほど(相対湿度が高いほど)、露点温度も高くなります。冬季に暖房を使用し、室内の温湿度が高くなると、少しの温度差で露点に達しやすくなります。
熱橋(ヒートブリッジ)と表面温度
熱橋(ヒートブリッジ)とは、断熱材が途切れている箇所や、断熱材よりも熱を伝えやすい構造材(柱、梁、コンクリートなど)を通じて、熱が移動しやすい部位を指します。
- ・熱橋の役割:熱橋部では、外気の影響が室内側に伝わりやすく、他の壁面よりも表面温度が低くなりがちです。これにより、室内の水蒸気が熱橋部に集中して結露を発生させます。
気密、換気、通気層の役割
- ・気密と防湿:結露を防止するには、室内からの水蒸気が壁内や屋根裏に入り込むのを防ぐ防湿層(気密シート)の施工と、気密性の確保が重要です。気密性が不十分だと、暖かく湿った空気が隙間を通じて壁内・屋根裏に侵入し、断熱材の冷たい層で結露する内部結露を引き起こします。
- ・換気:室内で発生する水蒸気(発湿)を排出するためには、計画的な換気が不可欠です。換気不足は相対湿度を上げ、結露リスクを高めます。
- ・屋根・外壁の通気層:屋根下や外壁材の裏側に設けられる通気層は、外部から浸入した雨水や、内部で発生した湿気を外部へ排出・乾燥させる役割を持ちます。通気層が適切に機能しないと、湿気が滞留し、内部結露や腐朽の原因となります。
症状の見分け方

擬似雨漏り(結露)と真の雨漏りは、発生パターンや痕跡に大きな違いがあり、それらを観察することが初期診断の鍵となります。
発生時期と天候との相関
結露(擬似雨漏り)
- ・季節:主に冬季(暖房を使用し、室内が高温高湿で、外気が低温時)や、梅雨〜夏季(多湿な外気が冷房された室内に入り込む、または夜間放射冷却で屋根が冷えた時)に発生しやすい。
- ・天候との相関:雨が降っていない日でも発生します。
雨漏り(浸水)
- ・天候との相関:大雨、長雨、または強風を伴う雨の時に発生する傾向が強いです。雨がやむと、漏水も比較的早く止まることがあります。
シミの位置・形状・材質別痕跡
結露痕跡
- ・位置:部屋の隅、窓枠の周囲、金属などの熱橋になりやすい部分の天井や壁際、小屋裏の野地板の裏側など、表面温度が低い箇所に発生しやすいです。
- ・痕跡:水分計で測定した際、躯体や内装材の含水率が極端に高い場合があります。
- ・におい:長期間放置された結露水による腐朽やカビが発生している場合、カビ臭がすることがあります。
雨漏り痕跡
- ・位置:発生箇所は必ずしも熱橋と一致しません。バルコニーの笠木と本体の取り合い部、サッシ上枠、屋根の谷樋周辺、架台固定部など、防水ラインの不連続な箇所の直下で浸出することが多いです。
- ・痕跡:浸出水が外装材や下地材の汚れを含んで着色している場合があります。
事前ヒアリングと記録

擬似雨漏りの診断において、建物の物理的な構造だけでなく、居住者の生活習慣(間診)のヒアリングは、原因を絞り込むための最も重要な情報源です。
ヒアリングによる発湿源と運用状況の把握
雨漏り診断の基本原則の第2原則は、「入居者に対し、間診を徹底する」ことです。結露診断では、以下の項目を詳しく聞き取ります。
- 1. 室内発湿源:浴室(換気扇の使用頻度、浴槽の残り湯の有無)、室内干し(頻度、量)、加湿器の使用状況(特に冬季の寝室など)、調理時の湯気の管理。
- 2. 暖房方式と運転状況:FF暖房、石油ストーブ(燃焼系は水蒸気を発生させる)、エアコンなど、使用している暖房方式、設定温度、運転時間。
- 3. 換気運用:24時間換気システムの運転状況(停止していないか、フィルタ清掃状況)、窓開け換気の頻度と時間。レンジフード使用時の給気口の開放状況(負圧による影響を排除するため)。
温湿度ログ化(簡易データの取り方)
精密な診断には専門機器が必要ですが、日常的に温湿度を記録するだけでも、結露リスクを評価できます。
- ・温湿度計の設置:室内(居室、特に結露が疑われる部屋)と小屋裏(点検口付近)に、データロガー機能付きの温湿度計を設置し、温度と相対湿度のログを継続的に取得します。
- ・露点温度の計算:取得した室内温湿度から露点温度を算出し、建材の表面温度がこの露点温度を下回っている可能性があるかを推定します。
室内診断
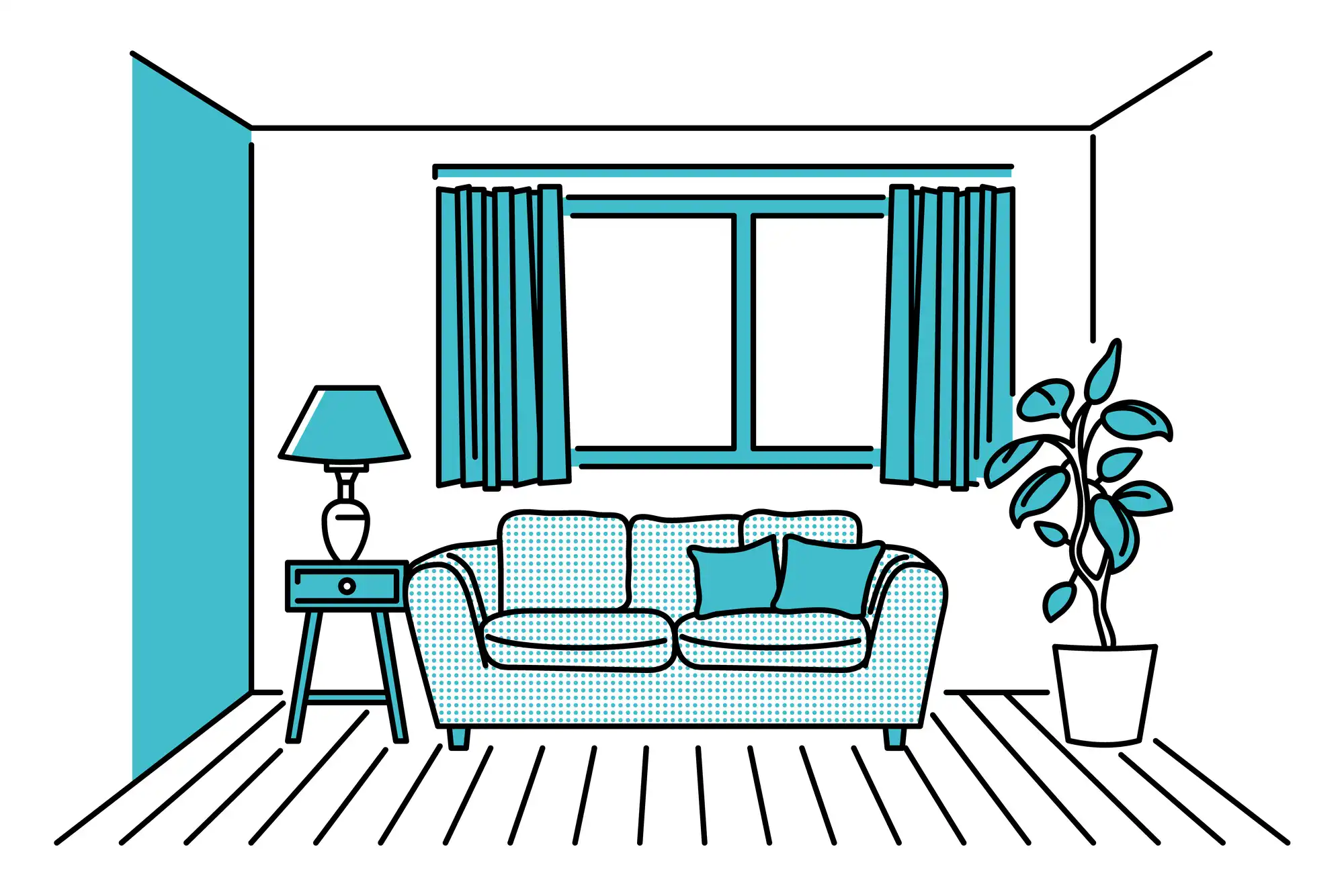
室内診断では、目視で確認できない表面温度の低下や湿度の異常、そして換気の不全を特定します。
赤外線サーモグラフィーカメラによる表面温度の可視化
- ・熱橋の特定:赤外線サーモグラフィーカメラ(赤外線カメラ)は、温度差を色別に可視化できるため、断熱欠損や熱橋により表面温度が低下している箇所を特定するのに非常に有効です。
- ・水の存在確認:結露や雨漏りにより濡れて温度が下がった箇所を感知できます。濡れている箇所は温度が下がるため、写真として明示することで、水の存在を確認できます。
換気設備の作動確認と室内環境評価
- ・換気設備のチェック:24時間換気システム(第1種・第3種)の吸気口および排気口が詰まっていないか、運転が停止されていないかを確認します。吸排気の風量を測定し、換気計画通りに作動しているかを確認することも重要です。
- ・CO₂濃度測定:室内換気量が不足していると、二酸化炭素(CO₂)濃度が高くなります。CO₂濃度を測定することで、換気能力の不足を客観的に評価できます。
その他の診断ツール
- ・水分計:天井や壁のシミが発生している箇所の石膏ボードや木部に対し、水分計を当てて含水率を測定します。高い含水率は、継続的な浸水(結露または雨漏り)の存在を示します。
- ・ルーパー:外壁のクラックやシーリングの切れ目など、小さな隙間を拡大して確認するために、ルーペが使用されます。
小屋裏・壁内の点検

擬似雨漏りの多くは、目に見えない小屋裏や壁内の断熱・気密・通気層の不備に起因する内部結露です。点検口を開けて、これらの部位を総点検する必要があります。
気流止めと断熱材の連続性
- ・気流止めの有無:壁内を通って湿気が小屋裏へ流れ込むのを防ぐための気流止め(ファイヤーストップ)が適切に施工されているかを確認します。気流止めがないと、壁内の湿った空気が小屋裏へ流れ込み、小屋裏結露の原因となります。
- ・断熱材の欠損・ずれ:断熱材が構造材との間に隙間なく充填されているか、経年や施工不良により断熱材が垂れ下がったり、ずれたりして断熱欠損が生じていないかを確認します。断熱材が連続していない箇所は熱橋となり、結露リスクが高まります。
屋根通気層の連続性と換気バランス
屋根下地(野地板)の裏側で結露が発生していないかを確認し、小屋裏換気(屋根通気)の経路が適切かを確認します。
- ・通気層の連続性:軒天換気口から外気を取り込み、小屋裏全体を通り、棟換気口や換気棟から排出する屋根通気層が、途中で断熱材によって閉塞されていないか、連続性が確保されているかを確認します。
- ・換気バランス:換気棟や軒天換気などの吸気口と排気口のバランス(吸気量と排気量)が適切であるかを確認します。吸排気のバランスが崩れていると、湿気が滞留しやすくなります。
野地合板の含水痕
小屋裏の野地板(屋根下地材)の裏側に、過去の結露や雨漏りによるシミ(含水痕)がないかを確認します。野地合板にシミがある場合、それが雨水浸入によるものか、小屋裏結露によるものかを切り分けます。
典型シナリオ別の原因推定
擬似雨漏りは、建物の物理的な欠陥と、特定の季節や生活習慣が重なることで発生します。
冬季の結露シナリオ
- ・原因:室内での暖房使用により室内温度が高くなり、同時に加湿器や室内干しにより室内湿度が上昇し、壁内や屋根裏の気密層に不備がある箇所で内部結露が発生します。
- ・症状:寒冷地や冬季に、壁や天井の隅、窓枠周辺など、熱橋部で水滴やシミが発生します。
夏季・梅雨時の結露シナリオ
- ・原因:高温多湿な外気が壁内通気層や小屋裏に入り込み、エアコンで冷やされた室内側の壁や天井裏の防湿層(または気密層)が冷やされ、外壁側や屋根通気層側で逆転結露に近い現象が発生するリスクがあります。また、夏の夜間に屋根が急激に冷やされる夜間放射冷却により、小屋裏で結露が発生することもあります。
- ・症状:梅雨〜夏季にかけて、天井裏や壁内に湿気が滞留し、シミやカビが発生します。
室内発湿源の過多による結露
- ・原因:浴室の使用後(換気扇停止)、室内干しの常態化、加湿器の過剰な運用などにより、室内の相対湿度が長時間高すぎる状態が維持されること。室内湿度が高いほど露点温度が上がり、結露しやすくなります。
- ・対策:室内湿度の目標をRH≤60%程度に維持することが、結露対策の目安となります。
レンジフード負圧による気流の影響
レンジフード(換気扇)を強運転すると、室内の空気が大量に排出され、室内の気圧が外部に対して低下する負圧状態が発生します。
- ・負圧吸引リスク:負圧状態になると、給気口が不足している場合、建物外周部の気密層や防水層の隙間(サッシ周り、換気口、電気配線貫通部など)から、外気や湿気が屋根裏・壁内へ強制的に吸引される現象が起こります。これにより、外部の冷たい空気や湿気が断熱層に触れ、局所的な結露を招くリスクがあります。
雨漏り調査との併用判断
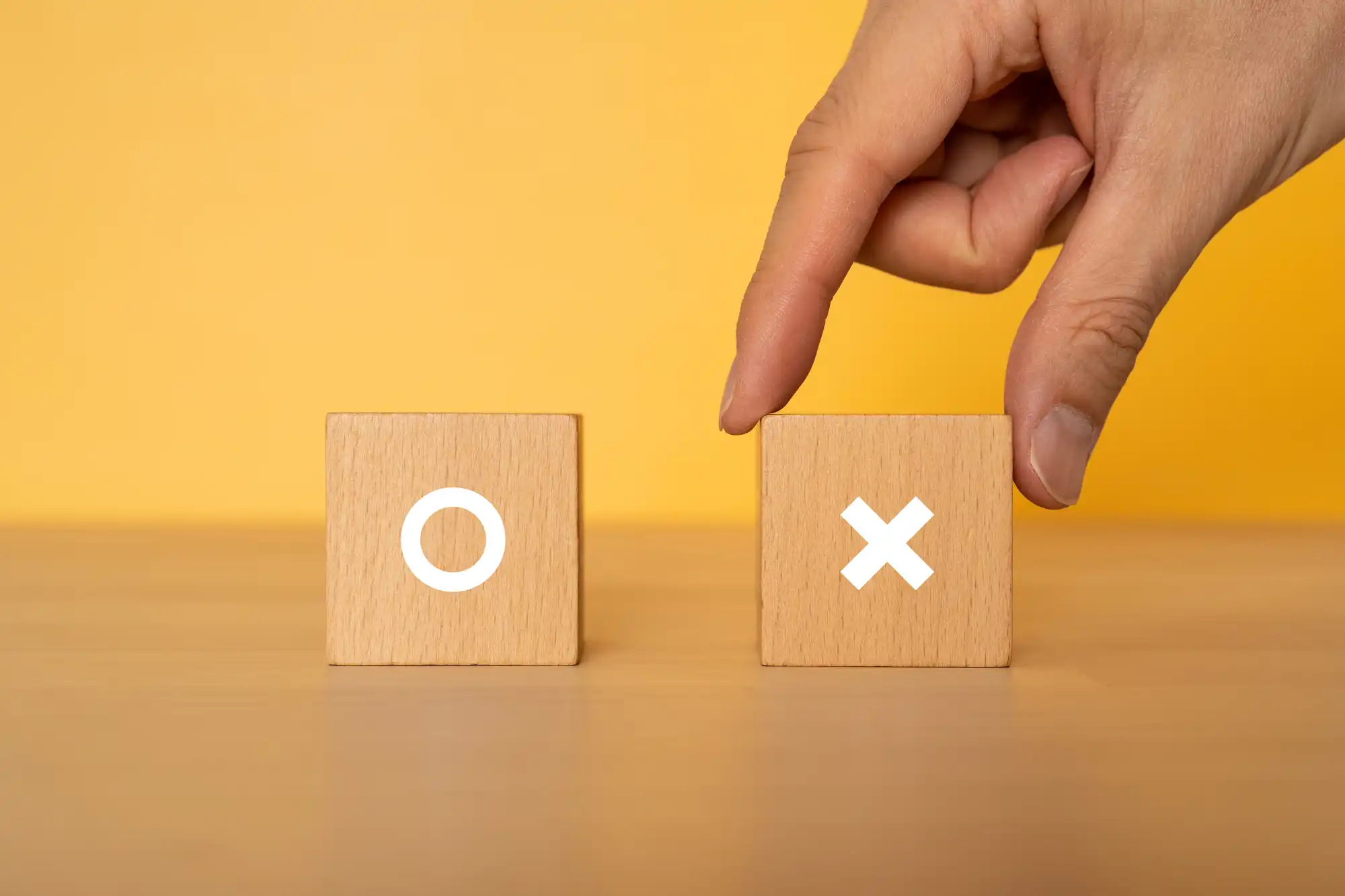
結露か雨漏りかの判断が難しい場合、特に強風時や大雨時にのみ発生する場合は、雨漏りの可能性を排除するために、散水試験を行う必要が生じます。
散水試験の適否
- ・適する場合:発生時期が雨天時と相関し、特に風向や風速が関与していると疑われる場合(例:南風の強い時のみ)、雨漏りによる浸水の可能性を排除するために散水試験を実施します。
- ・不適な場合:冬季の結露が疑われる場合や、室内環境(湿度、温度)に依存して発生していると強く推定される場合、散水試験は不要であるか、結露診断が優先されます。
タイムラグの観察
雨漏りが発生した場合、水が屋根材の下のルーフィングから下地、そして室内まで到達するのにタイムラグが生じます。
- ・タイムラグの計測:降り始めから漏水するまでのおおよその時間(例:1~2時間、3時間以上)を計測します。このタイムラグは、水が屋根や壁の内部を流下している経路の存在を示唆し、雨漏りの可能性を高めます。
偽陽性・偽陰性を避ける進め方
- ・偽陽性:結露が原因なのに、安易な散水試験で水が隙間から浸入し、「雨漏り」だと誤診してしまうこと。これを避けるには、散水前に温湿度や熱橋を特定し、結露による水分でないことを確認します。
- ・偽陰性:雨漏りなのに、散水量が不足したり、風圧を再現できなかったりして、漏水が再現されないこと。特に強風時の吹き込みが原因の場合、散水試験だけでは再現が難しいことがあります。
是正設計
擬似雨漏りの根治は、断熱・気密・換気の三要素を総合的に是正する建築物理学的な設計是正が必要です。
断熱補強と熱橋対策
- ・断熱材の連続性確保:断熱材が途切れている箇所(熱橋部)を特定し、断熱材を増し打ち・増し張りするなどして補強し、断熱層の連続性を確保します。
- ・熱橋対策:窓枠周り、筋交い、間柱など、熱を伝えやすい構造材が外気に晒されやすい部位には、内側または外側から断熱材を補強し、表面温度の低下を防ぎます。
気密層の連続化と貫通部処理
- ・気密層の施工:室内で発生した水蒸気が壁内・屋根裏に入り込むのを防ぐため、防湿層(気密シート)の施工を徹底し、気密層の連続化を図ります。
- ・貫通部の処理:コンセントや配線、配管などの貫通部から湿気が侵入しないよう、気密テープや専用の気密パッキンを用いて、貫通部の気密処理を確実に行います。
小屋裏換気量の適正化と屋根通気経路の再構築
小屋裏や屋根通気層内の湿気を排出するために、換気計画を是正します。
- ・小屋裏換気量の適正化:軒天換気口(吸気)と換気棟(排気)の換気量を算出し、不足している場合は、換気棟の増設や軒天換気口の拡張を行います。吸気口と排気口のバランス(吸気量と排気量)を適切に保つことが重要です。
- ・屋根通気経路の確保:断熱材が通気層を閉塞している箇所がないかを確認し、通気スペーサーなどを利用して、軒先から棟までの通気経路を再構築します。片流れ屋根の棟頂部のように、雨漏りが発生しやすい部位には、防雨効果のある換気部材を組み込んだ棟包みを設けることが対策として挙げられています。
屋根材・構法別の要点

建物の構法や屋根材によって、結露の発生しやすさや是正の勘所が異なります。
在来工法・2×4工法における気流止めと断熱材
- ・在来工法・2×4:在来工法や2×4工法では、断熱材(グラスウールなど)を柱間に充填する充填断熱が一般的です。充填断熱では、断熱材が垂れ下がったり、壁との間に隙間が生じたりすると、気流が発生しやすくなり、内部結露のリスクが高まります。
- ・気流止め:壁内からの気流が小屋裏へ流れ込むのを防ぐ気流止めの施工が、小屋裏結露防止のために不可欠です。
高気密高断熱住宅の注意点
高気密高断熱住宅(C値、Q値が良好な住宅)は、結露リスクが低いとされていますが、換気計画の不備や気密層の欠損がある場合、局所的な結露が発生し、被害が拡大しやすい傾向があります。
- ・換気システムの不具合:計画換気(第1種換気など)の給排気バランスが崩れると、負圧が生じて外部の湿気を吸引したり、室内湿度が高止まりしたりするリスクがあります。
- ・レンジフードの負圧:レンジフードを運転する際、給気口を開放せずに運転すると、負圧により湿気が壁内から吸引され、結露を招くリスクがあります。
屋根材別の通気対策の要点
- ・瓦屋根:瓦屋根は瓦とルーフィングの間に通気層が存在します。この通気層から湿気を外部へ排出できる透湿ルーフィング(JIS A 6111適合品)を選定することで、下地の湿気を透湿させ、屋根材と下葺き材の間から湿気を排出できます。
- ・金属屋根(立平葺き):立平葺きは、緩勾配でも施工できるため多用されますが、勾配屋根の平部からの漏水事故の46%を占めるほど、漏水リスクが高い部位です。緩勾配ゆえに水や湿気が滞留しやすく、通気層の連続性の確保と、水密性の高い改質アスファルトルーフィングの採用が重要となります。
運用での改善策
結露リスクを低減するためには、設計是正だけでなく、居住者による適切な運用管理が非常に重要です。
換気システムの適切な運用
- ・24時間換気の継続:24時間換気システムは停止せず、継続して運転することが必須です。
- ・フィルタ清掃:換気口や換気扇のフィルタが目詰まりしていると、換気能力が低下し、室内の湿度が高止まりします。定期的なフィルタ清掃が必要です。
- ・レンジフード使用時の給気:レンジフード使用時には、必ず専用の給気口(または窓)を開け、負圧による意図しない箇所からの空気の吸引を防ぎます。
室内発湿管理と露点回避
- ・発湿源の排除:浴室の使用後や調理後は、すぐに換気扇を運転し、室内干しは極力避けるか、換気を徹底して行います。
- ・加湿器の調整:特に冬季に加湿器を使用する場合、室内の相対湿度が上がりすぎないよう注意します。
- ・露点回避の目安:室内温度と相対湿度の組み合わせで、壁や窓の表面温度が露点温度を下回らないよう管理します。一般的に、冬季には室内湿度の目標をRH≤60%程度に維持することが、結露対策の目安となります。
費用・工期レンジ
結露(擬似雨漏り)の調査および是正費用は、原因の特定度合いと、是正範囲(部分的な断熱補強か、屋根通気構造の全面改修か)によって大きく変動します。
費用レンジ(一般的目安)
| 工事内容 | 費用目安(税別) | 備考 |
|---|---|---|
| 原因調査(サーモ、水分計、散水) | 10万~30万円 | 専門的な診断士による調査。原因特定に必須。 |
| 小屋裏換気改善(換気棟・軒天換気口の増設) | 10万~40万円 | 足場費用は別途必要。小屋裏の湿気対策。 |
| 断熱材の部分補強・気流止め是正 | 15万~50万円/箇所 | 内装解体・復旧費、断熱材充填、気密テープ施工含む。 |
| 屋根通気層の再構築・断熱補強 | 50万~150万円 | 屋根材の一部剥がし、通気層確保、ルーフィング是正。 |
| 仮設費用(足場設置) | 600~900円/m² | 高所作業が伴う場合に必須。 |
| 内装復旧費 | 10万~50万円 | 漏水・結露による汚損、カビ・腐朽除去後の内装復旧。 |
工期レンジとリスク
- ・部分是正(換気・断熱補強):1週間〜2週間程度。
- ・屋根通気層の改修(屋根上部作業):2週間〜1ヶ月程度。
- ・工期リスク:建築物理的な是正工事(断熱材の充填、気密層の施工)は、天候リスク(雨天、強風)のほか、気密テープやシーリングの適切な乾燥・硬化時間を確保するために、ゆとりのある工程が必要です。
業者選び・FAQ・まとめ
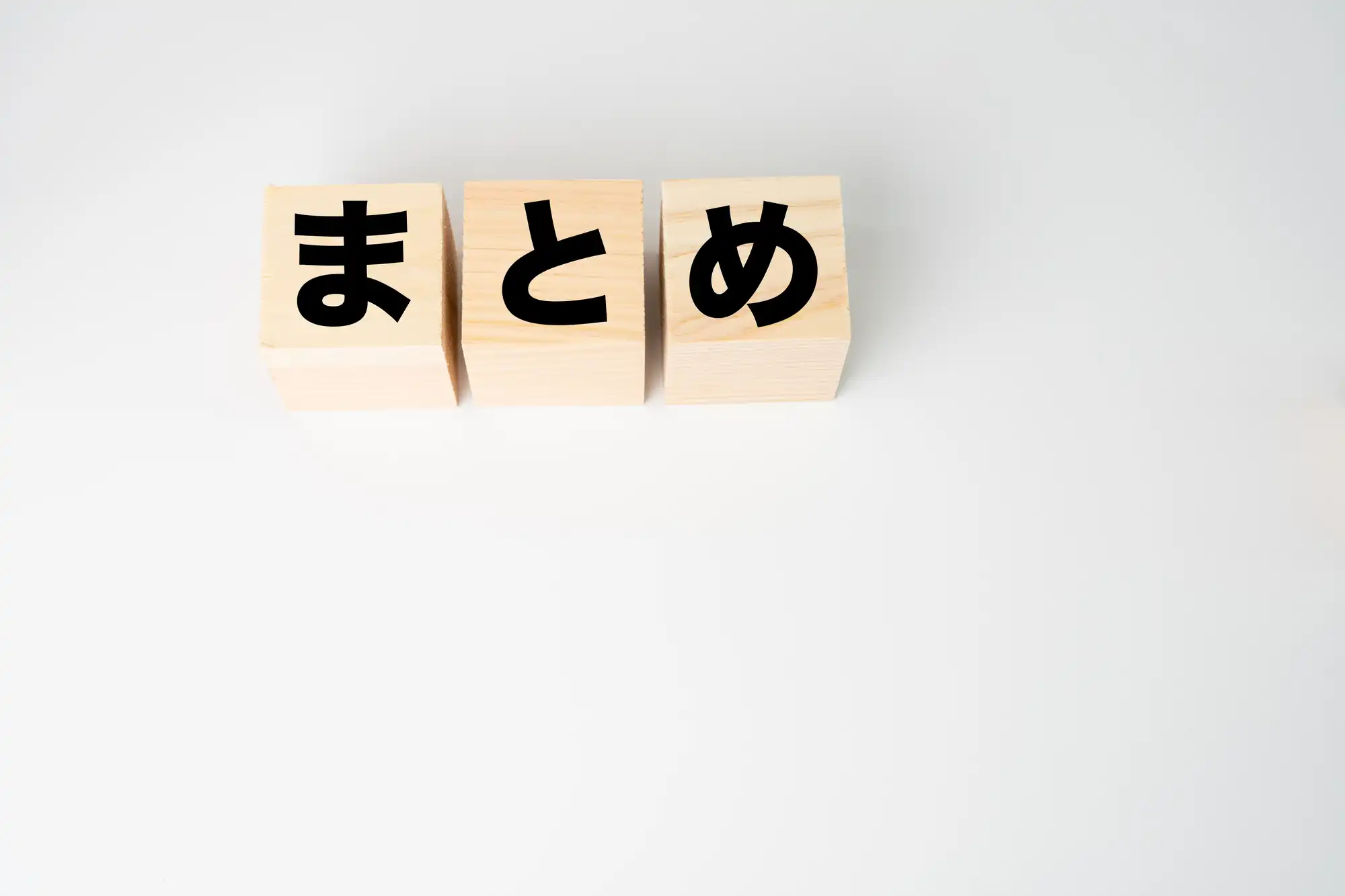
擬似雨漏りの解決には、屋根や外壁の防水技術だけでなく、断熱、気密、換気という建築物理学的な専門知識が必須です。専門的な知見を持つ業者(雨漏り診断士など)を選ぶことが重要です。
業者選びの質問チェックリスト
- 1. 診断の専門性:結露と雨漏りのメカニズムの違いを明確に説明でき、サーモグラフィーや温湿度計を用いた定量的な診断を提案できるか。
- 2. 設計提案:単なる補修ではなく、断熱補強、気密層の連続化、換気計画の是正など、構造的な是正設計を提案できるか。
- 3. 記録と保証:施工前に詳細な仕様書や工程表を提示し、工事中の写真台帳を作成するか、そして適切な保証(瑕疵担保責任保険など、10年保証)を提供できるか。
- 4. 第三者機関の活用:業者の説明に不安がある場合、日本建築家協会(JIA)などの第三者機関に相談することを検討すべきです。
FAQ(よくある質問と回答)
Q1. 冬季の加湿器運用は、どの程度の相対湿度まで許容できますか?
A. 結露を避けるための室内湿度の目標として、冬季は相対湿度(RH)を60%以下に保つことが望ましいです。室内湿度が高いほど露点温度が上昇し、断熱が不十分な箇所(熱橋)で結露が発生しやすくなります。加湿器を使用する場合は、温湿度計で湿度を確認しながら、過剰にならないよう注意が必要です。
Q2. 小屋裏の結露対策として、換気棟の追加設置は有効ですか?
A. 換気棟の追加設置は有効な対策の一つですが、単に追加するだけでは不十分です。小屋裏換気は、軒天換気(吸気)と換気棟(排気)のバランスが重要です。換気棟を追加する場合は、軒天換気口からの吸気量が排気量に見合っているかを確認し、吸排気経路(通気層)が断熱材によって閉塞されていないか(通気層の連続性)を確認することが必須です。
Q3. 断熱材の種別によって、湿気対策の勘所は異なりますか?
A. はい、異なります。一般的に、断熱材が湿気を含んでしまうと断熱性能が低下します。特に、繊維系の断熱材(グラスウールなど)を使用する場合、室内側から湿気が侵入するのを防ぐために、気密シート(防湿層)を連続させて施工し、内部結露を防ぐことが極めて重要です。断熱材の性能を維持するためには、防湿・気密の施工が不可欠です。
Q4. レンジフードを運転すると、屋根裏から雨漏りするようなシミが出るのはなぜですか?
A. それは、レンジフードの強運転による負圧が原因である可能性があります。負圧状態になると、給気口が不足している場合、外部の冷たい空気が、屋根や壁のわずかな隙間(サッシ周り、配線貫通部など)から強制的に吸引されます。この冷たい空気が断熱層の内側の冷えた部材に触れると、結露が発生し、それが水滴となって天井などにシミを作るのです。換気中は必ず給気口を開放し、負圧状態を解消する必要があります。
Q5. 散水試験をしても雨漏りが再現しない場合、結露と断定してよいですか?
A. 結露と断定するには、さらなる調査が必要です。散水試験で再現しない場合、原因が風圧を伴う吹き込みや、非常に長い時間の降雨に依存している(偽陰性)可能性が残ります。しかし、同時に、雨が降っていない季節や時間帯に発生している、または熱橋部で発生している場合は、結露の可能性が極めて高いです。結露か雨漏りかの最終判断は、サーモグラフィー診断や温湿度ログによる「熱橋・露点」の特定と、小屋裏・壁内の断熱・気密層の目視点検の結果を総合的に判断して行います。
まとめチェックリスト
- 1. 症状の切り分け:シミや滴下が雨天時のみか、冬季や梅雨時など特定の季節に発生しているかを把握し、結露(擬似雨漏り)の可能性を評価しましたか。
- 2. 診断の実施:サーモグラフィーカメラや水分計を用いて、表面温度の低下(熱橋)や、建材の異常な含水率を確認しましたか。
- 3. 小屋裏の点検:小屋裏に入り、断熱材の欠損・ずれ、気流止めの有無、屋根通気層の連続性を確認しましたか。
- 4. 換気・気密の是正:換気システムのフィルタ清掃や適切な運転を確認し、壁内への湿気侵入を防ぐための気密層(防湿層)の連続化と貫通部処理を計画しましたか。
- 5. 生活習慣の是正:加湿器の使用や室内干しを控え、室内湿度をRH≤60%以下に抑える運用改善策を検討しましたか。
- 6. 業者選定:建築物理(断熱・気密・換気)と屋根防水の両方に精通し、是正設計を提案できる専門業者を選びましたか。