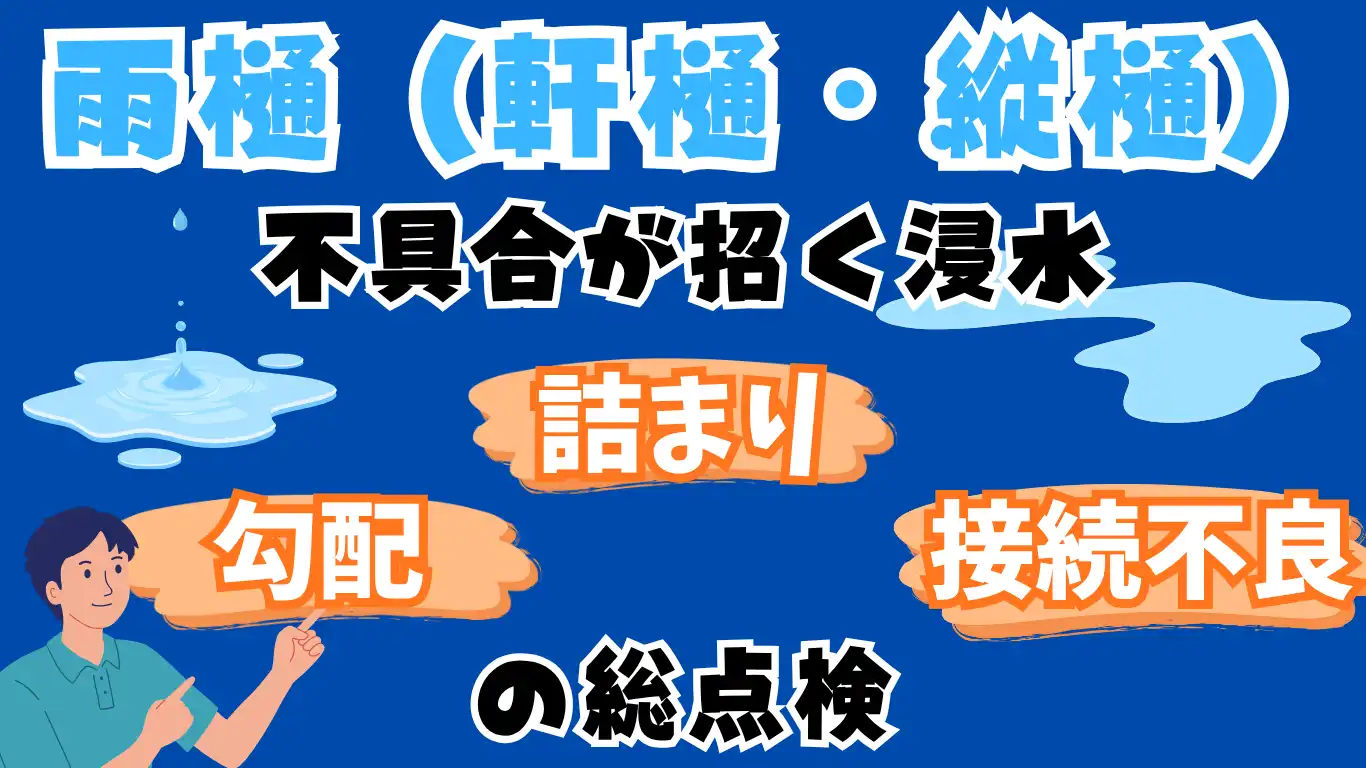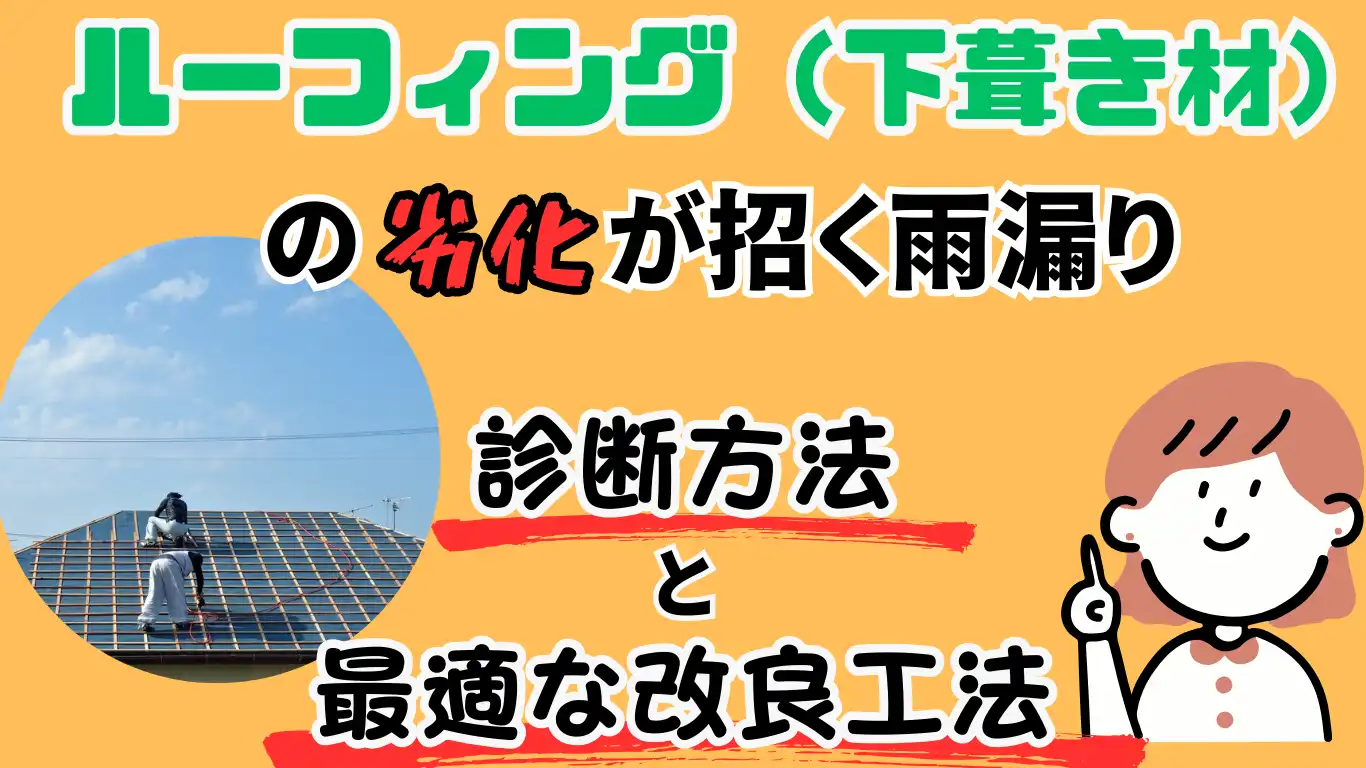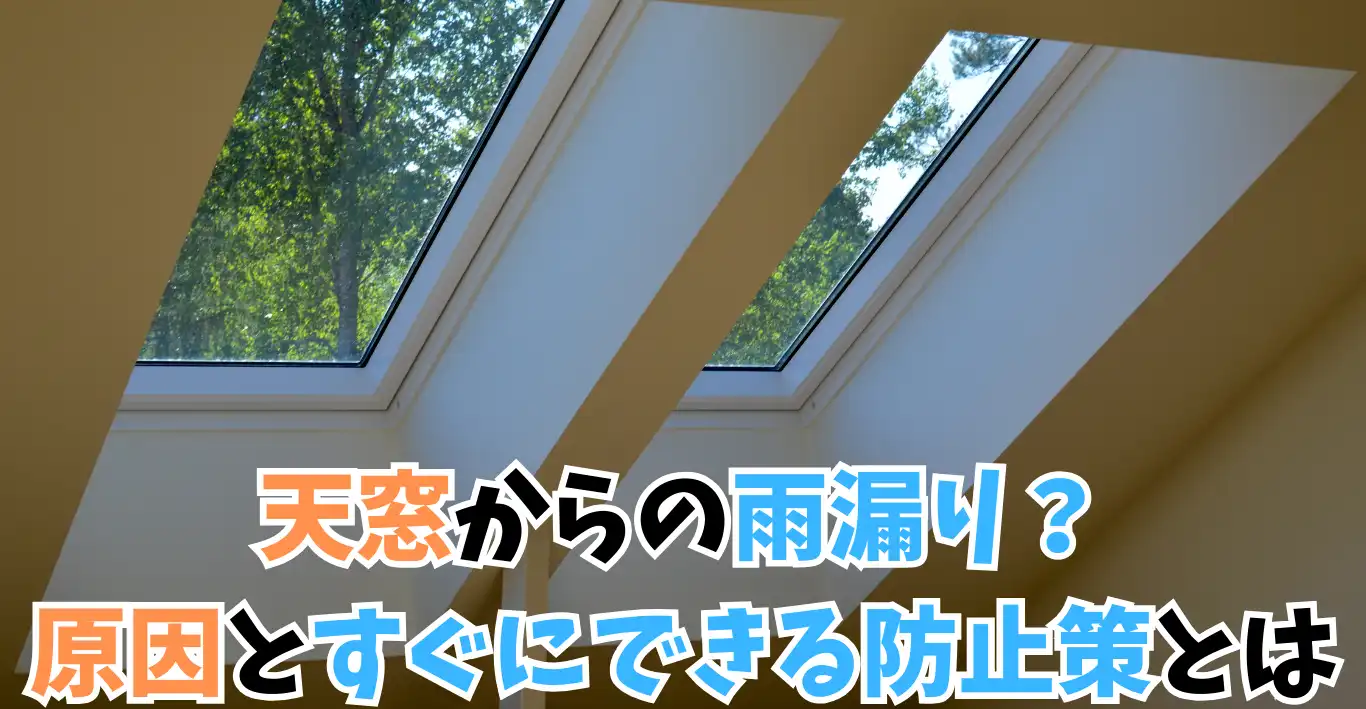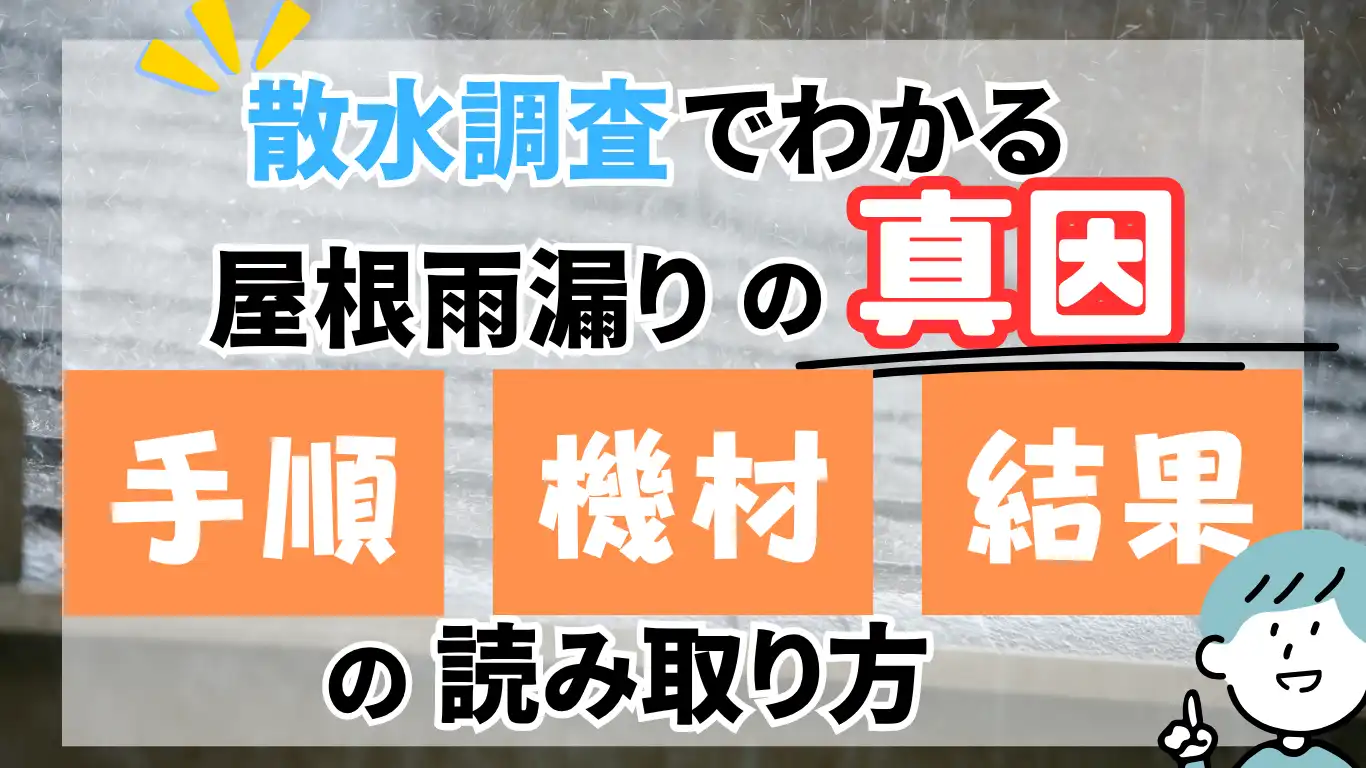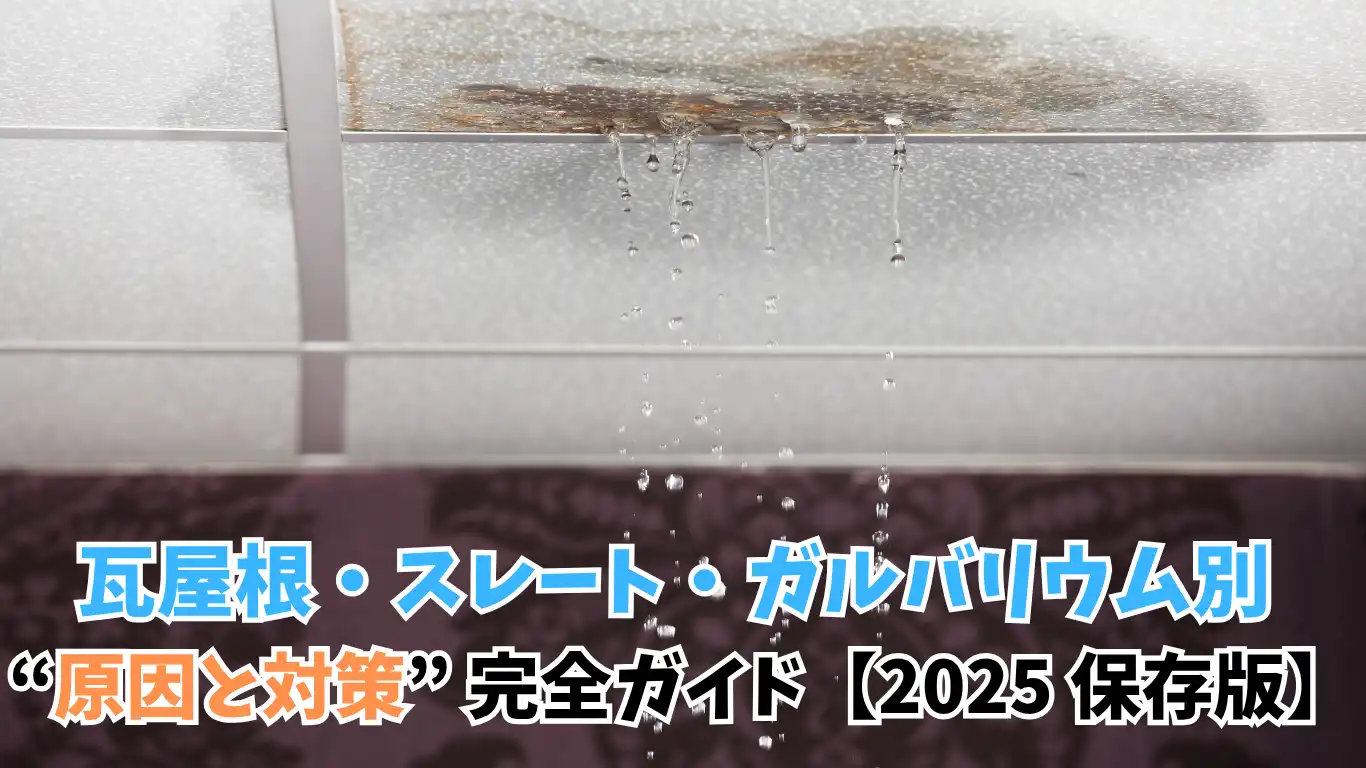戸建て住宅の雨漏りは、屋根材の劣化だけでなく、地味ながら建物の水の流れを司る雨樋の不具合が原因となっているケースが非常に多いです。
特に築10〜40年の住宅では、雨樋詰まり、勾配不良、接続不良によるオーバーフローが外壁や軒先からの浸水を引き起こし、深刻な雨漏りへと発展します。
本コラムでは、雨樋の不具合が招く浸水メカニズムと、オーナー様ができる点検・対策を平易に解説します。
雨樋は「勾配・通水・接続」を整えれば室内浸水の多くを防げる

住宅の外周を守る雨樋は、「軒樋(軒先に沿った樋)が水を適切に流す勾配」、「縦樋(垂直の樋)までのスムーズな通水」、そして「部材間の接続の健全性」という3つの要素を整えることで、雨漏りや室内浸水に至るリスクの多くを予防・解消できます。
雨樋の不具合は、屋根から落ちる水を制御できなくなり、設計上防水性能が弱いとされる軒先や外壁の取り合い部分へ、直接大量の水を流し込んでしまうからです。特に雨樋オーバーフローが発生すると、水が軒天や外壁の裏側へ回り込み、透湿防水シート(壁内部の二次防水)やルーフィング(屋根の二次防水)のわずかな不備を突いて浸入し、構造材の腐朽(腐ること)につながるリスクが高まります。
台風や集中豪雨の際に、軒樋が詰まりや逆勾配で機能不全を起こすと、軒樋から水がオーバーフローして軒天を伝い、小屋裏や壁内に浸入します。この水は、外壁と屋根が交わる取り合い部分など、施工がやり難い要注意部位で浸入経路を見つけやすく、深刻な雨漏りへと発展し、場合によっては数百万円規模の修理費用(例:構造事故では974万円の修理費用例がある)が必要となる可能性もあります。
ひとことまとめ:
雨樋は単なる装飾ではなく、建物全体の雨仕舞い(あまじまい:雨水の処理)の要です。「勾配・通水・接続」を定期的にチェックし、雨樋オーバーフローを未然に防ぎましょう。
症状の見分け方:外回りのサイン(溢れ・しみ・苔)と室内のサイン(天井の輪染み 等)

雨樋の不具合は、まず外回り(軒先、外壁)で「水が溢れる」「筋状の汚れが付く」といった明確なサインを出します。
これらの初期サインを見逃さずに対処することが、室内への浸水(天井の輪染みなど)を食い止める最善の方法です。
軒樋がオーバーフローすると、水は外壁を伝って流れ落ちます。
この水には土埃や排気ガスなどが含まれているため、特定の箇所に水の通り道ができ、筋状の黒い汚れや苔、藻が発生します。
これらの汚れは、水が意図しない場所に流れ、外壁塗装の耐久性を低下させたり、建物の内部へ浸水する危険があることを示しています。
具体例:
・外回りのサイン:
- 豪雨時の滝状の溢れ:軒樋が詰まりや逆勾配で水の排水能力を超え、水が軒樋を乗り越えて滝のように流れ落ちる(雨樋 オーバーフロー)。
- 筋状の汚れ・苔:縦樋の継手(つなぎ目)や集水器の接続不良から水が漏れ、外壁に沿って黒い線や苔が生じている。
- 軒天のシミ・剥がれ:軒樋の裏側や軒天に輪染みや塗膜の剥がれが発生している場合は、軒樋から軒天への浸入が始まっている可能性が高い。
・室内のサイン:
- 天井や壁の輪染み:軒樋 オーバーフローした水が軒天を通って小屋裏に浸入し、室内側の天井や壁にシミ(輪染み)となって現れる。特に壁際のシミや、雨漏りがひどいときには床に水たまりができる事例も報告されている。
ひとことまとめ:
雨樋は「無言の通訳者」です。外壁のシミや苔は、雨樋のどこかに不具合があるという重要なメッセージだと受け止めましょう。
仕組みの超入門:軒樋 → 集水器 → 縦樋 → 排水の流れとボトルネック
雨樋システムは、軒樋、集水器(ドロップ)、縦樋という3つの主要部品で構成され、屋根面で集めた雨水を確実に地上へ導くためのシンプルな経路ですが、この経路の中でも集水器(水を落とす部品)とエルボ(曲がり角の部品)が詰まりや接続不良を起こしやすいボトルネックとなります。
屋根材の上を流れる水は、落ち葉や砂、泥などの異物を含んでおり、これらが水の流れを変える場所や、経路が細くなる部分(集水器やエルボ)で引っかかりやすいためです。
これらのボトルネックで雨樋詰まりが発生すると、軒樋全体で水の大渋滞が起こり、排水能力を失い、最終的にオーバーフローを引き起こします。
水の流れの経路
- 1. 軒樋(のきどい):屋根の軒先に沿って取り付けられ、屋根面全体から流れ落ちた水を受け止め、受け金具に支えられながら一定の勾配で集水器へ誘導する。
- 2. 集水器(しゅうすいき/ドロップ):軒樋の終端、または途中に設けられ、水平の軒樋から垂直の縦樋へ水流を切り替える接続部。形状が細いため、落ち葉などの異物が最も溜まりやすい場所(ボトルネック)となる。
- 3. 縦樋(たてどい):集水器から垂直に地上へ伸び、雨水を側溝や浸透マスへと排水する。建物の角や壁面を伝うため、途中にエルボ(L字型の曲がり角)が用いられる。
ひとことまとめ:
雨樋のシステムでは、特に集水器とエルボの部分で詰まりによる「大渋滞」が発生しやすいため、ここを重点的に点検しましょう。
準備と安全:飛散・感電・転落を避ける/近隣配慮/記録のコツ
雨樋は高所に位置するため、点検・修理を行う際は、転落事故や感電、資材の飛散といったリスクを避けるため、オーナー様ご自身での高所作業は絶対に避け、専門業者に安全管理を徹底して依頼し、オーナー様は近隣への配慮と記録の準備に徹することが重要です。
雨樋は通常、軒先やベランダの屋根など、地上から数メートル以上の高さに設置されており、特に脚立や屋根上での作業は滑落の危険が非常に高いです。また、縦樋が電線付近を通過している場合もあり、感電のリスクもあります。
オーナー様が事前に準備すべきこと
- 1. 高所作業の回避(専門業者へ):電線付近や強風時の作業は危険。専門業者は安全帯の着用や適切な足場(または脚立)の確保、そして飛散対策(防護ネットなど)を徹底する。
-
2. 近隣への配慮:
・工事車両の駐車スペースの確保や、作業音、資材の飛散について、事前に近隣住民に説明し、理解を得ておく。 ・雨樋から排出される水が、隣家の敷地や排水経路に影響を与えないよう、一時的な養生や水の誘導も必要。 - 3. 記録(写真台帳)の準備:室内外のシミの位置や、雨樋がオーバーフローしている様子の写真を可能な範囲で撮影し、写真台帳として整理しておくと、専門業者への原因特定の依頼がスムーズになる。
ひとことまとめ:
雨樋の調査・修理は命に関わる高所作業です。安全管理を徹底し、オーナー様は記録と近隣配慮に注力しましょう。
点検手順

雨樋の点検は、オーナー様が安全に実施できる地上からの目視を基本とし、勾配不良や詰まりのサインを遠隔で発見します。
詳細な確認や高所の接続不良の確認は、脚立やドローンを使用する専門業者に依頼する手順を踏むべきです。
雨樋の不具合の多くは、地上からでもオーバーフローや接続不良による外壁の汚れとして確認できるため、まず安全な場所から情報を収集し、その情報を基に専門業者の調査範囲を絞り込むことが、効率的かつ安全な点検につながります。
点検の手順と確認ポイント
-
1. 地上からの目視(普段の生活の中で):
・大雨時に軒樋から水がオーバーフローしていないか、縦樋の排水能力が追いついているかを確認。
・縦樋と外壁の間に、常に筋状の汚れや苔がないかを確認し、継手や集水器からの接続不良を疑う。 -
2. 窓や双眼鏡による遠隔観察:
2階の窓から軒樋の内部を覗き、落ち葉や泥が溜まっていないか(詰まり)、水が集水器へ向かって流れるべき方向に逆勾配になっていないかを確認。 -
3. 専門業者による詳細調査:
脚立や高所カメラ(ドローン)を用いて、受け金具の緩みや破損、集水器やエルボなどの接続部の劣化状況を詳細に確認し、写真台帳として記録する。
ひとことまとめ:
雨樋は目線より高い位置にあるため、安全な地上から時間をかけて観察し、詳細調査は専門業者の知見と道具を活用しましょう。
勾配不良の見抜き方と直し方:逆勾配/たわみ/金具ピッチの見直し
雨樋の勾配不良は、軒樋が集水器に向かって適切に傾斜していない状態(逆勾配)や、経年により受け金具の力が弱まりたわみが発生した状態を指します。
これを是正するためには、劣化した受け金具の交換やピッチ(間隔)の見直し、または勾配調整という恒久対策が必要です。
軒樋は、わずかながらも集水器へ向かって傾斜している必要があります。
勾配が不適切だと水が途中で溜まり(水たまり)、その重みでさらに軒樋がたわみ、排水能力が低下し、溜まった水がオーバーフローを引き起こすからです。
勾配不良の兆候と直し方
-
1. 逆勾配(水が溜まる):
・見抜き方:晴れた日に軒樋の途中や、集水器とは逆の端に水が溜まっている場合(逆勾配=水が流れにくい「上り坂」になっている状態)は、勾配不良。
・直し方:受け金具を外し、勾配が水平1mあたり数ミリ(推奨される勾配)となるように、受け金具の位置を調整し直す。 -
2. たわみ(U字型の変形):
・見抜き方:軒樋のラインが一直線ではなく、中央部分が下に垂れ下がっている(たわみ)場合は、受け金具の劣化か、受け金具の間隔(ピッチ)が広すぎることが原因。
・直し方:既存の受け金具に加え、たわんだ箇所に新しい受け金具を増設して補強し、勾配を修正する。
不具合 → 対処の早見表(勾配・詰まり関連)
| 症状 | 想定原因 | 一次対応 | 恒久対策 |
|---|---|---|---|
| 軒先で溢れる(豪雨時) | 詰まり/逆勾配 | 落ち葉やごみ除去 | 勾配調整・防葉ネット設置 |
| 軒先で水たまりがある(晴天時) | 逆勾配/受け金具のたわみ | なし(応急処置不可) | 受け金具の交換・増設による勾配調整 |
ひとことまとめ:
勾配不良は放置すると軒樋の破損につながります。受け金具の点検・調整は専門業者に依頼し、確実な直し方で排水能力を維持しましょう。
詰まり対策:落ち葉・泥・鳥の巣・氷結/防葉ネット・清掃周期・集水器の形状見直し

雨樋詰まりの主原因は、落ち葉、土砂、鳥の巣、および寒冷地での氷結です。
これらの詰まりを防ぎ、オーバーフローを回避するためには、防葉ネットの設置による予防と、定期的な清掃周期の設定、そして集水器の形状を見直すことが重要です。
雨樋の詰まりは、水の流れを完全に遮断し、排水能力をゼロにするため、屋根に降った雨水が全てオーバーフローし、軒先や外壁に流れ込むことになります。
詰まりは特に集水器やエルボといったボトルネックで起こりやすいです。
詰まりの種類と対策
-
1. 落ち葉・泥:
・原因:庭木や周囲の山林からの落ち葉、屋根材の表面から流れてきた土砂や泥が溜まる。
・対策:軒樋の上に防葉ネットを被せることで、落ち葉の侵入を大幅に防げる。 -
2. 鳥の巣:
・原因:鳥が軒樋や集水器の周辺に巣を作り、詰まりを引き起こす。
・対策:定期的な点検時に巣を除去し、侵入防止対策を講じる。 -
3. 氷結(多雪地域):
・原因:多雪地域では、軒樋内に溜まった水が凍りつき、排水経路を塞いだり、氷の重みで軒樋が破損したりする。
・対策:軒樋にヒーター(凍結防止ヒーター)を設置するか、雪の重みに耐えられる金属製の雨樋(10章参照)を選択する。
集水器(水を落とす部品)の排水能力が低い場合は、集水器の径を大きくしたり、構造を見直すことで詰まりにくくすることも有効です。
ひとことまとめ:
雨樋詰まりは最も防ぎやすい不具合です。防葉ネットなどを活用し、集水器を清潔に保ち、排水能力を最大限に引き出しましょう。
接続不良の典型:継手の隙間・エルボのズレ・集水器の割れ→応急と恒久策
雨樋の接続不良(継手、エルボ、集水器の隙間や割れ)は、軒樋を伝って流れてきた水を外壁に直接吹き付けてしまい、外壁に筋状の汚れやカビ、さらには壁内部の浸水を引き起こします。
応急処置として防水テープが有効ですが、抜本的な修理のためには部品の交換や適切な位置調整による恒久策が必要です。
雨樋の部材は、熱による伸縮や強風による振動、あるいは経年劣化により、継手やエルボの接続が緩んだり、破損したりすることがあります。
これらの接続不良箇所からは、水が継続的に漏れ出し、外壁の防水性能が弱い部分(サッシ周りなど)に水の浸入を許してしまうからです。
接続不良の典型的なケースと対処法
-
1. 軒樋の継手の隙間:
・症状:軒樋のつなぎ目から水が滴り、真下の外壁に筋状の汚垂れができる。
・一次対応(応急):濡れていても貼れる防水テープなどで一時的に隙間を塞ぐ。
・恒久対策:新しい継手に交換し、適切な接続部材でしっかりと固定する。 -
2. 集水器の割れ・破損:
・症状:集水器本体にひび割れや割れがあり、大量の雨水が流れ落ちる。
・恒久対策:集水器を新しいものに交換。この際、集水器と縦樋の接続部が外壁から適切に離れるよう調整する。 -
3. 縦樋の受け金具からの外れ:
・症状:強風(風災)により縦樋が受け金具から外れ、宙吊りになっている、または壁から離れて水が飛び散る。
・恒久対策:縦樋を元の位置に戻し、受け金具を増設するなどして強固に固定する。
不具合→対処の早見表(接続・排水関連)
| 症状 | 想定原因 | 一次対応 | 恒久対策 |
|---|---|---|---|
| 外壁に筋状の汚れ | 継手の隙間/エルボのズレ | 防水テープ応急 | 継手交換・位置調整 |
| 縦樋が宙吊り | 強風による外れ | 紐などで一時固定 | 受け金具の補強・交換 |
| 豪雨時だけ浸水 | 排水能力不足 | 集水器の一時拡張 | 縦樋追加・合流分散 |
ひとことまとめ:
接続不良は雨漏りの直接的な原因となりえます。応急処置後は、必ず恒久策を講じましょう。
排水能力の再設計:縦樋の本数・径・合流分散・オーバーフロー口・地上排水の導線
多雨地域や近年増加している集中豪雨(ゲリラ豪雨)に対応するため、既存の雨樋の排水能力が不足している場合は、縦樋の本数や径を増やしたり、オーバーフロー口(逃げ道)を設けるなど、建物の排水能力の再設計を検討することが、雨樋 オーバーフローによる室内浸水を防ぐために非常に有効です。
現在の住宅は、設計時の想定を上回る短時間の集中豪雨に頻繁にさらされており、既存の雨樋では水の処理が追いつかず、オーバーフローによる浸水リスクが高まっています。
特にベランダや陸屋根のドレン(排水口)は、詰まりによって満水状態になると、防水層の立ち上がり部から容易に水が浸入し、重大な雨漏り事故に直結する危険性があります。
排水能力を向上させるための再設計のポイント
-
1. 縦樋の増設・径の拡大:
軒樋の長さが長い場合、集水器と縦樋の接続箇所を増やし、水流を分散(合流分散)させる。縦樋の径(直径)を大きくすることも有効。 -
2. オーバーフロー口の設置(ベランダ/陸屋根):
ベランダのドレン(排水口)が詰まりなどで機能しなくなった際に、水が防水層の立ち上がりを越えて室内に浸入するのを防ぐため、オーバーフロー管(逃げ道)を設けて、屋外へ排水する経路を確保する。 -
3. 地上排水の導線確認:
縦樋から排出された水が、建物の基礎や土台に溜まったり、隣地に流れ込んだりしないよう、側溝や浸透マスへの導線を明確にする。
ひとことまとめ:
排水能力の再設計は、雨樋に万が一の詰まりやオーバーフローが発生した際の「水の逃げ道」を確保する、非常に重要な安全策です。
材質・形状別の注意:塩ビ半丸/角樋/金属樋のクセと耐久性
雨樋には主に塩化ビニル樹脂系(塩ビ)、金属系(ガルバリウム鋼板、銅など)があり、それぞれ形状(半丸、角樋)にも種類があります。
材質や形状によって、耐久性、熱伸縮、凍害への耐性が異なるため、地域特性(多雪、沿岸強風)や屋根材との相性を考慮した選択とメンテナンスが重要です。
雨樋は常に紫外線や風雨にさらされており、材質の特性によって劣化の進行度や、破損しやすい箇所が異なります。
特に塩ビ製は安価ですが熱伸縮が大きく、継手部分に隙間が生じやすい傾向があり、金属製は耐久性が高い反面、接続部の板金との納まり(雨仕舞いの取り決め)に注意が必要です。
材質・形状別の注意点
-
1. 塩化ビニル樹脂系(半丸/角樋):
・特徴:安価で軽量。設置が容易。
・注意点:紫外線や熱による劣化で硬化しやすく、継手部分で伸縮による隙間が生じやすい。多雪地域では、雪の重みや氷結による割れや変形に注意。 -
2. 金属系(角樋など):
・特徴:高い耐久性、デザイン性が高い。
・注意点:設置時の加工には専門技術が必要であり、特に板金との接続部(軒先板金など)で、雨水が裏側に回り込むような施工不良がないか確認が必要。
ひとことまとめ:
雨樋の材質は、耐久性だけでなく、接続不良のリスクにも影響します。定期点検の際に、継手部分や受け金具の緩みがないか確認しましょう。
取り合いの要点:屋根の谷・ベランダ・ドレン・外壁との境目で起きやすい漏れ

雨樋の不具合によって浸水が発生する際、水の浸入経路となりやすいのは、屋根の谷、ベランダのドレン(排水口)、外壁と軒先の境目など、異なる構造体が接する「取り合い」部分の防水の弱点です。
雨樋オーバーフローが発生した水は、屋根材の二次防水層(ルーフィングや透湿防水シート)の納まりを試すように流れます。
取り合い部分は、複数の工種が複雑に交わるため、施工がやり難い要注意部位であり、防水処理(立ち上がり、水切り)の不備がある場合が多いからです。
具体例:
・ベランダ・陸屋根のドレン:ドレン(排水口)の詰まりにより満水状態になると、防水層の立ち上がりを越えて水が笠木や手すり壁の取り合い部から浸入することがあります。防水層の立ち上がりは床から120mm以上が目安とされています。
・軒先と外壁の境目:軒の出が小さい(軒ゼロ)屋根は、雨樋オーバーフローや強風による雨水の巻き込み(逆水)に対し、軒先まわりの透湿防水シートの納まりが不十分だと、躯体側への雨水浸入を招きやすいです。
ひとことまとめ:
雨樋のトラブルは、ベランダ ドレンの詰まりや軒先の防水層(立ち上がりなど)の弱点を顕在化させます。修理の際は、これらの取り合い部分も点検しましょう。
費用・工期の目安:規模×高さ×足場の有無×部品交換の有無

雨樋の修理費用は、詰まりや接続不良の部分補修であれば数万円で収まりますが、建物の高さや軒樋の交換、勾配の抜本的な調整には足場の設置が必要となり、その場合は数十万円以上の費用となり、工期も延びるため、足場設置の判断は慎重に行うべきです。
雨樋は高所に位置するため、安全性を確保するための足場設置費用が、修理費用全体の大部分を占めることが多いからです。
足場を組む場合は、他の外壁や屋根のメンテナンス(塗装、シーリング打ち替えなど)を同時に行う(同時工事)ことで、足場費用の経済的な負担を軽減できます。
雨樋修理の費用と工期の目安(概算)
| 規模 | 小(1〜2カ所) | 中(3〜5カ所) | 大(面全体) |
|---|---|---|---|
| 想定費用 | 3万〜10万 | 10万〜30万 | 30万〜100万以上 |
| 工期 | 半日〜1日 | 1〜2日 | 2〜3日(足場除く) |
| 主な作業 | 詰まり解消、継手交換 | 軒樋の部分交換、勾配調整 | 軒樋・縦樋全面交換 |
| 備考 | 高さ・足場で変動 | 足場なしの場合 | 足場設置費用が別途必要 |
高所作業(特に2階以上)や電線付近の作業には、安全確保のため足場または専門的な脚立を使用する専門業者へ依頼してください。
ひとことまとめ:
雨樋修理の費用は、足場の有無で決まります。他のメンテナンスとの同時工事を検討し、コスト効率を高めましょう。
業者選び・見積・保証/まとめとFAQ(Q1〜Q5)

雨樋の不具合は、建物の雨仕舞い全体の問題を映し出している可能性があるため、雨樋だけでなく屋根・外壁の防水・構造の知見を持ち、原因特定(勾配、詰まり、接続不良)に基づいた抜本的な修理を提案し、長期的な保証を提供できる専門業者を選ぶことが、再発防止の鍵となります。
雨漏りは施工の意図に反し、建物内部に雨水が浸入することと定義されており、雨樋の不具合によるオーバーフローは、外壁や軒天といった二次防水層の弱点を突いて浸水を引き起こします。
安易に漏れている箇所をシーリング材などで塞いだだけでは、時間の経過とともに雨漏りが再発する可能性が高いです。
そのため、雨樋の修理は、根本的な原因を見極める専門業者に依頼すべきです。
業者選びでは、以下の点を質問・確認しましょう。
- 1. 原因特定能力:詰まり清掃だけでなく、勾配不良や接続不良の真の原因を地上や高所カメラ(ドローン)による調査で特定し、写真台帳で明確に報告できるか。
- 2. 修理内容:軒樋の排水能力向上策(縦樋の径の拡大、集水器の増設など)や、オーバーフローした場合の外壁・軒天取り合い部の点検を提案しているか。
- 3. 保証:施工後の雨樋本体や接続部に対して、長期的な保証(例:5年~10年)を提供できるか確認する。
高所作業の安全管理:
屋根上での調査や修理は高所作業であり、滑落や感電のリスクを伴います。必ず、安全帯の着用や足場の設置など、安全管理を徹底できる専門業者に依頼してください。
ひとことまとめ:
雨樋修理は、単なる部品交換ではなく、建物の雨仕舞いを見直すチャンスと捉え、原因特定に強い信頼できる業者を選びましょう。
FAQ(Q1〜Q5)
Q1:雨樋 詰まりは自分で清掃できますか?
A1:1階の低い位置の軒樋や縦樋であれば、安全を確保して清掃できる場合がありますが、2階以上の高所や脚立作業が必要な場合は、転落や感電の危険があるため、絶対にオーナー様ご自身で行わず、専門業者に依頼してください。特に電線が近い場合は危険です。
Q2:雨樋の勾配はどのくらいが適切ですか?
A2:軒樋は、集水器に向かって水が流れるように、水平1mあたり数ミリ程度の下がり勾配が一般的です。この勾配が逆になっている状態(逆勾配)や、受け金具の緩みによるたわみは、詰まりやオーバーフローの原因となります。
Q3:雨樋の不具合は火災保険で修理できますか?
A3:雨樋の破損が台風による風災、雹被害、または大雪による雪災など、突発的な自然災害による外力が原因であると立証できれば、火災保険の補償対象となる可能性があります。経年劣化のみの場合は適用外です。
Q4:集水器が詰まりやすいのですが、何か対策はありますか?
A4:集水器は軒樋から縦樋への接続部であり、落ち葉や泥が最も溜まりやすいボトルネックです。軒樋全体に防葉ネットを設置することで、落ち葉による詰まりを予防できます。
Q5:雨樋のオーバーフローを放置すると、具体的に建物へどんな悪影響がありますか?
A5:オーバーフローした水が軒先や外壁を伝うと、外装材(塗装、シーリング)の劣化を早めるだけでなく、水が軒天裏や壁内部の透湿防水シートの弱点(取り合い部や貫通部)から浸入し、小屋裏や壁内の構造材を腐朽(腐ること)させたり、シロアリ被害を招いたりする可能性が高まります。
最終チェックリスト
- ・安全確保:高所作業は専門業者に依頼し、安全帯、足場、飛散防止対策を徹底しているか。
- ・勾配と通水:軒樋に水たまりや逆勾配、詰まりがないか、大雨時にオーバーフローしていないか確認したか。
- ・接続部の健全性:継手、エルボ、集水器に隙間や割れ、接続不良による外壁の汚垂れがないか確認したか。
- ・排水能力:集中豪雨時にも排水能力が追いついているか。ベランダのドレンにはオーバーフロー管が設置されているか。
- ・記録の徹底:室内外の被害状況(輪染み、汚れ)を写真台帳で記録し、修理業者へ正確に情報を伝えたか。